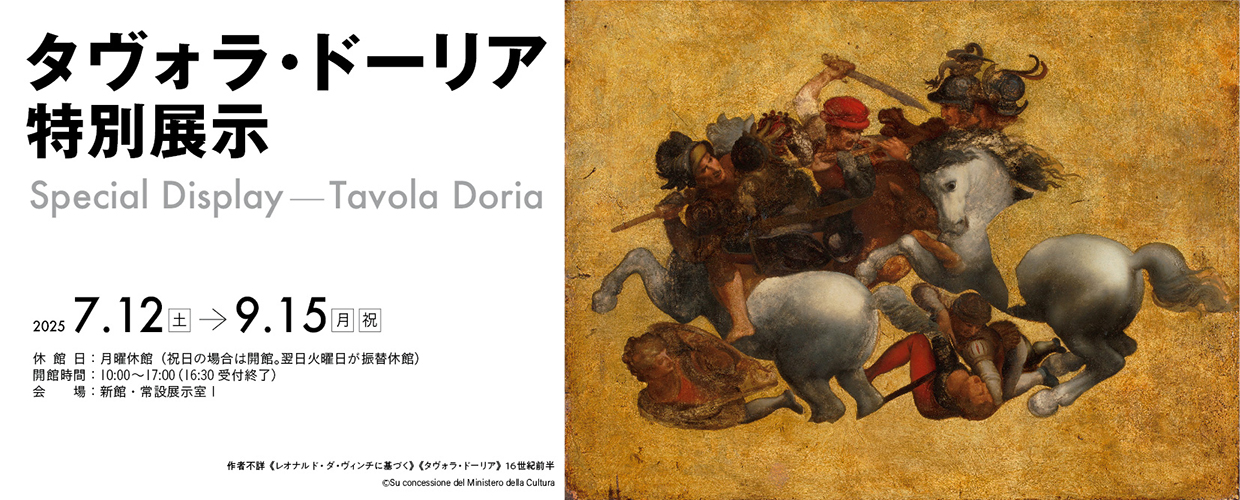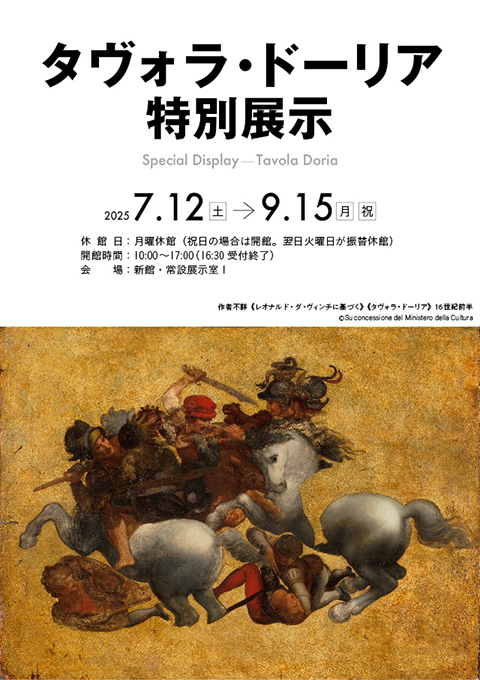昭和18年(1943)/絹本着色 軸装(双幅)
129.0×42.4cm
SUMMARY作品解説
「楠公父子」とは鎌倉・南北朝時代の武将楠木正成(右幅)とその息子正行(左幅)のこと。正成は後醍醐天皇の討幕運動に加担し、幕府と敵対。本作は正成が最期を遂げる湊川の合戦を前にした桜川での父子の別れの場面に因む。父正成は行く先のある息子正行に後事を託し再起を期待した。右左幅共に「鉄線描」といわれる強弱の少ない簡明な描線と薄い彩色を用いて、厳粛な場面にふさわしい静謐な画調を作り上げている。外遊が契機となり、日本の古典に改めて目を向けた契月は《経正》、《敦盛》(いずれも京都市京セラ美術館蔵)をはじめ、こうした清澄な歴史画を自らの仕事の一つとした。また同時期に《大楠公》(足立美術館蔵)、《小楠公弟兄》(京都市京セラ美術館蔵)、《楠公》(金蓮寺蔵)も手がけている。
ARTIST作家解説
菊池契月
Kikuchi Keigetsu1879-1955
長野に生まれる。はじめ南画家の児玉果亭に学び、17歳の時、京都に出て内海吉堂に師事。翌年、四条派の菊池芳文の塾に移る。師の勧めで第4回新古美術品展に出品した《文殊》(所蔵先不明)が褒状一等を受賞。明治39年(1906)、師芳文の娘あきと結婚、菊池姓を名乗る。翌年、文展が新設されてより出品を続け、受賞を重ねた。大正7年(1918)、芳文の死去と共に京都市立絵画専門学校教授に就任。同年、京都市に命ぜられ渡欧。エジプト彫刻やルネサンス絵画、キュービズム絵画などに感銘を受け、翌年帰国。京都画壇において四条派を継承しつつ、鉄線描を用いた理知的で高雅な画風を確立した。帝室技芸員、帝国芸術院会員などを歴任。京都市立絵画専門学校校長も務める。
同じ作家の作品一覧
INFORMATION作品情報

2020年6月1日 (月)~7月5日 (日)
日本美術の巨匠たち 島根県立美術館(島根、松江市)
2019年11月2日 (土)~12月22日 (日)
絵画でランデヴー−東西美術の出逢い− 和泉市久保惣記念美術館(大阪、和泉市)
2017年4月29日 (土)~6月25日 (日)
東京富士美術館コレクション −美の東西− 新居浜市美術館(愛媛、新居浜市)
2014年11月15日 (土)~1月18日 (日)
日本絵画の精華 高崎市タワー美術館(群馬、高崎市)
2013年3月16日 (土)~5月8日 (水)
近代日本画の精華 新潟県立近代美術館(新潟、長岡市)
2010年10月16日 (土)~11月28日 (日)
日本画に見る四季の美展 大観から玉堂、清方、松園まで ニューオータニ美術館(東京、千代田区)
1998年5月1日 (金)~6月30日 (火)
日本名画文物展—日本美術400年史・桃山時代〜近代 国父記念館(台湾、台北)
EXPLORE作品をもっと楽しむ

全国の美術館・博物館・アーカイブ機関を横断したプラットフォームでコンテンツを検索・閲覧でき、マイギャラリー(オンライン展覧会)の作成などができます。