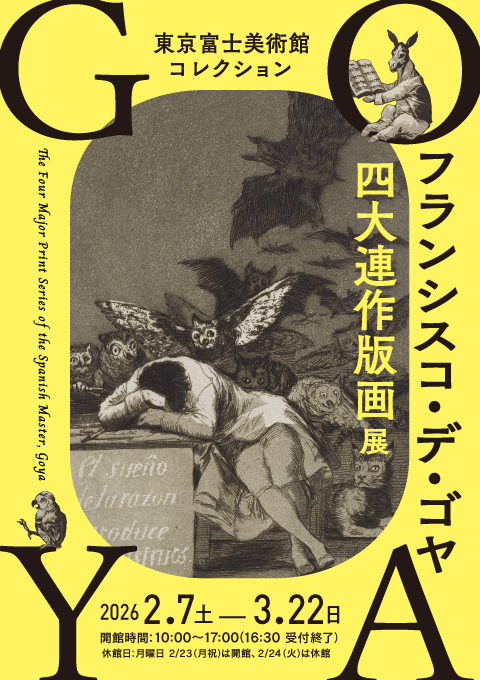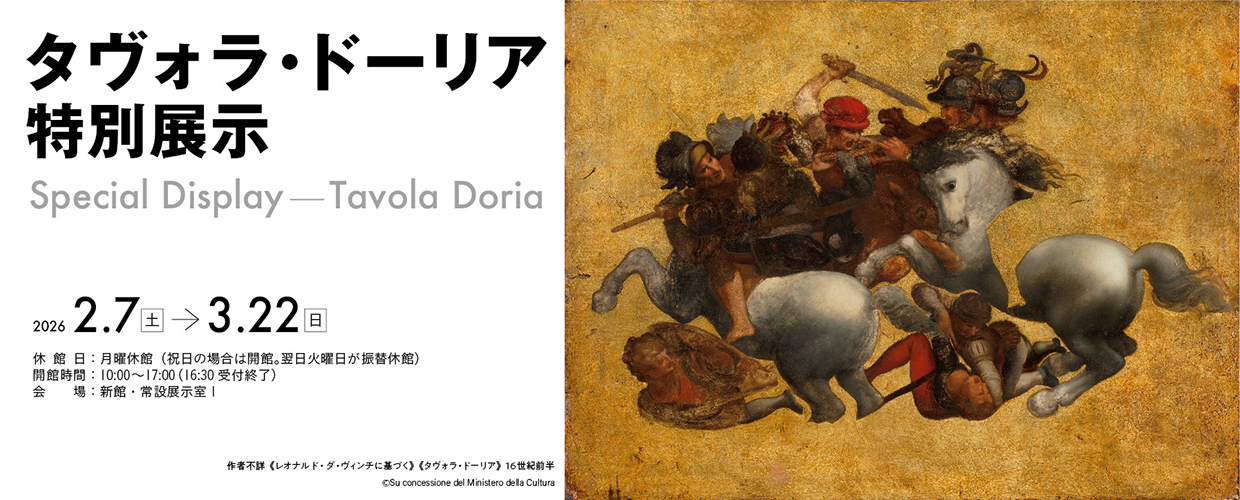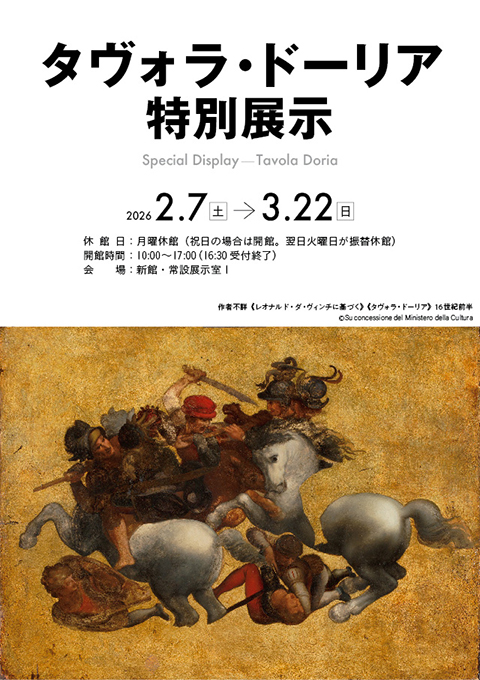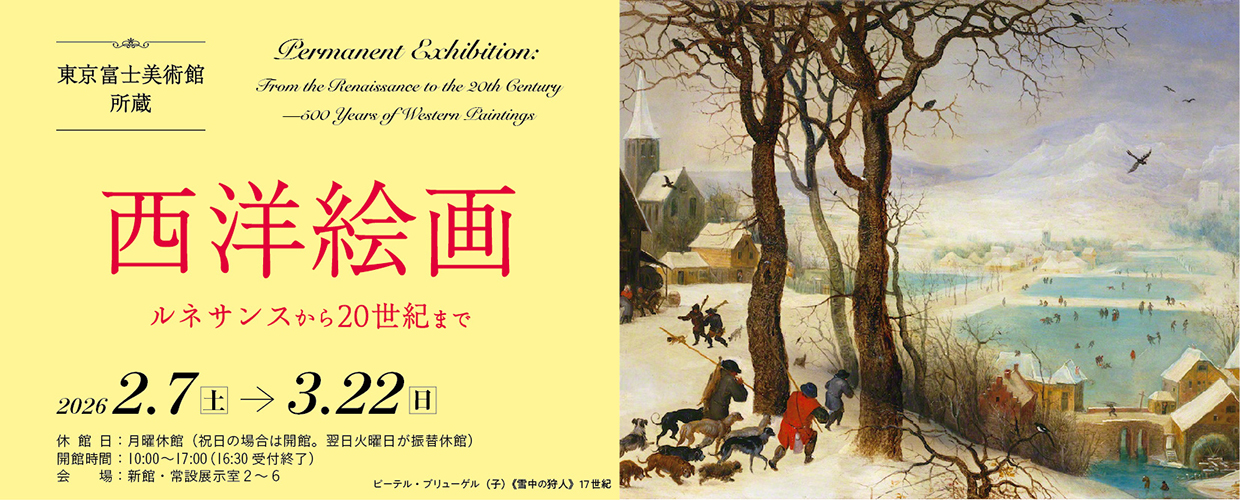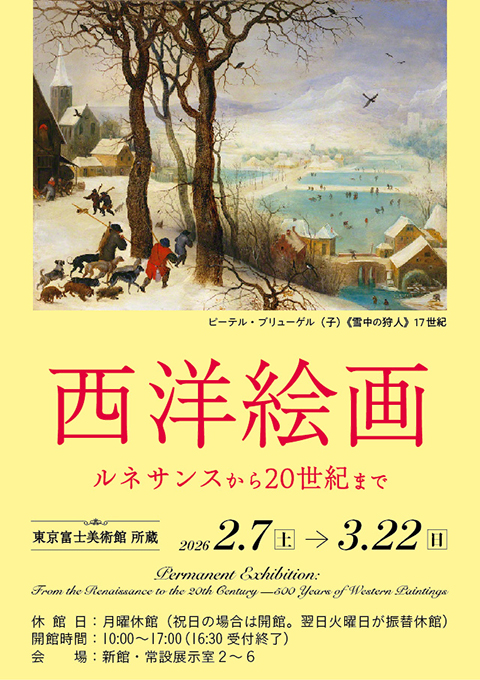SUMMARY作品解説
鮮やかな紅葉の中で3羽のシジュウカラと思われる小禽が戯れている。紅葉した葉はそれぞれ赤の色合いに細心の注意を払い彩色されている。一番左に描かれた小禽の首を上げる姿は自身が第11回文展に出品した《春禽趁晴図》(所蔵先不明)の中にも見ることができる。紅葉の葉や幹に輪郭線はなく、隈取りの技法を上手く使い、見事に表現している。落款・印章から、制作は渡欧から帰国した直後の大正10年(1921)頃から昭和初期にかけてと推測される。麦僊は渡欧を通して、改めて日本美術の奥深さや美しさを再考することができたという。それは本作のような日本画特有のぼかしの効果を駆使したような作品からも窺え、新鮮な気持ちで、日本画の制作を楽しんでいるようにも感じられる。
ARTIST作家解説
土田麦僊
Tsuchida Bakusen1887-1936
新潟県佐渡に生まれる。16歳で鈴木松年に入門。翌年には竹内栖鳳の塾へ移り、「麦僊」の号を受ける。第10回新古美術品展で《清暑》(新潟県立近代美術館・万代島美術館蔵)が4等賞3席、第2回文展では《罰》(京都国立近代美術館蔵)が3等賞を受賞した。明治42年(1909)、京都市立絵画専門学校が開校され、同門の小野竹喬とともに別科に入学。同期には村上華岳、榊原紫峰、野長瀬晩花、入江波光らがいた。同43年(1910)、美術史家の田中喜作を主宰とした「黒猫会(ル・シャノワール)」の結成に参加。後期印象派をはじめ西洋美術の動向を知る機会ともなった。同44年(1911)、卒業制作でもあった《髪》(京都市立芸術大学芸術資料館蔵)を第5回文展に、大正元年(1912)には八丈島に取材した《島の女》(東京国立近代美術館蔵)を第6回展にそれぞれ出品し、いずれも褒状を受ける。その後も文展に《海女》(第7回展/京都国立近代美術館蔵)、《散華》(第8回展/大阪中之島美術館蔵)、《大原女》(第9回展/山種美術館蔵)など、西洋美術と日本画の融合を図るかのような作品を次々と発表した。しかし、第11回展では中国の院体画を思わせる《春禽趁晴図》(所蔵先不明)が無賞に終わり、竹喬や華岳も落選となり、かねてより募っていた文展審査に対する不満が噴出。翌7年(1918)、竹喬、華岳、紫峰、晩花らと新団体「国画創作協会」を設立し、第1回国画創作協会展(以下、国展)に《湯女》(東京国立近代美術館蔵)を出品し、話題を呼んだ。同10年(1921)10月、竹喬、晩花らと渡欧し、フランス、イタリアなどを歴訪。この渡欧を通じて日本美術のもつ美しさを再考することとなった。翌13年(1924)には第4回国展に代表作《舞妓林泉図》(東京国立近代美術館蔵)を出品。その後も国展に出品を重ねるが、第7回展をもって国画創作協会・第1部(日本画部)は解散する。以後、竹喬とともに帝展に出品。昭和4年(1929)、第10回帝展では《罌粟》(宮内庁三の丸尚蔵館蔵)が宮内庁買上げとなった。またこの頃、所属の垣根を超えた展覧会が多く催され、中でも七絃会、清光会には意欲的に参加する。同8年(1933)、朝鮮で取材を行った《平牀》(京都市京セラ美術館蔵)を第14回帝展に出品。晩年に向かい麦僊の絵画はより平明になり、簡素な中に典雅な雰囲気を持った画風へと変化する。同9年(1934)、帝国美術院会員に推挙。同10年(1935)、帝国美術院の改組問題が起こり、麦僊は事態収拾に奔走する。同11年(1936)6月、膵臓癌のため49歳で没。
同じ作家の作品一覧
INFORMATION作品情報

2020年6月1日 (月)~7月5日 (日)
日本美術の巨匠たち 島根県立美術館(島根、松江市)
2013年3月16日 (土)~5月8日 (水)
近代日本画の精華 新潟県立近代美術館(新潟、長岡市)
EXPLORE作品をもっと楽しむ

全国の美術館・博物館・アーカイブ機関を横断したプラットフォームでコンテンツを検索・閲覧でき、マイギャラリー(オンライン展覧会)の作成などができます。