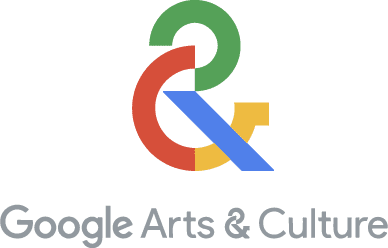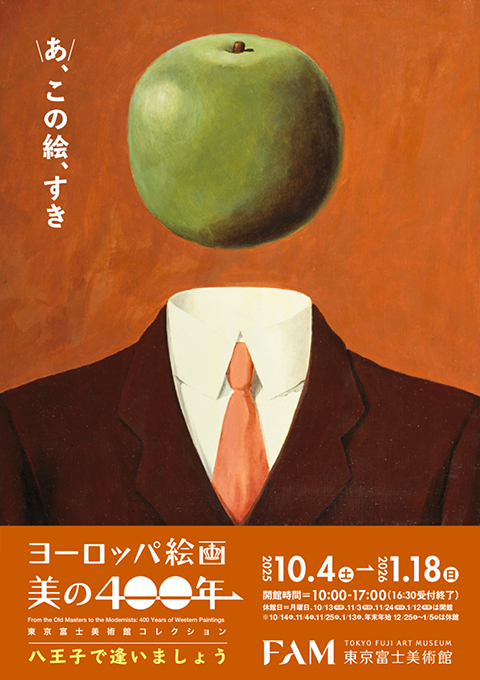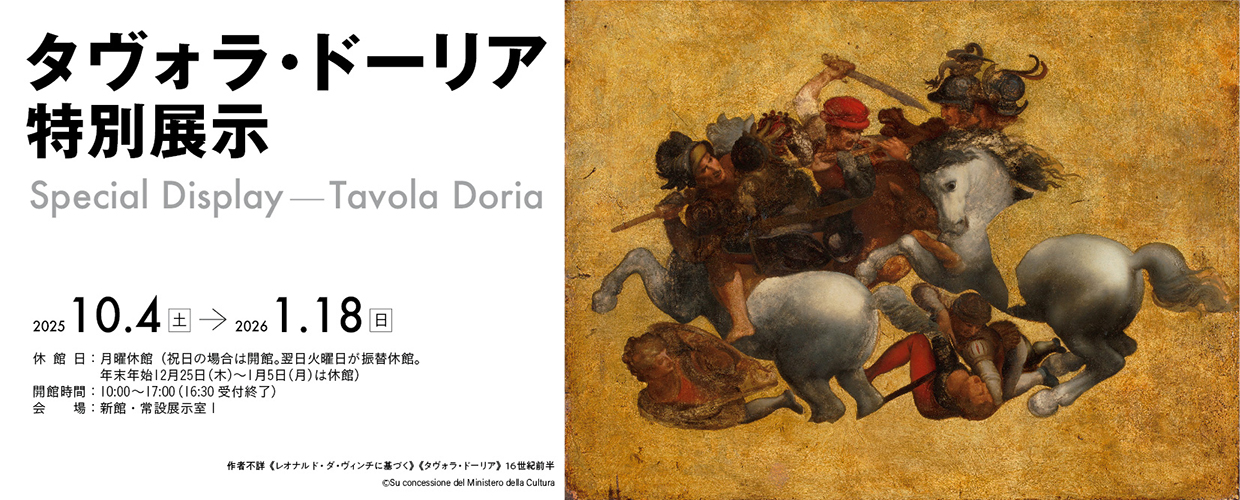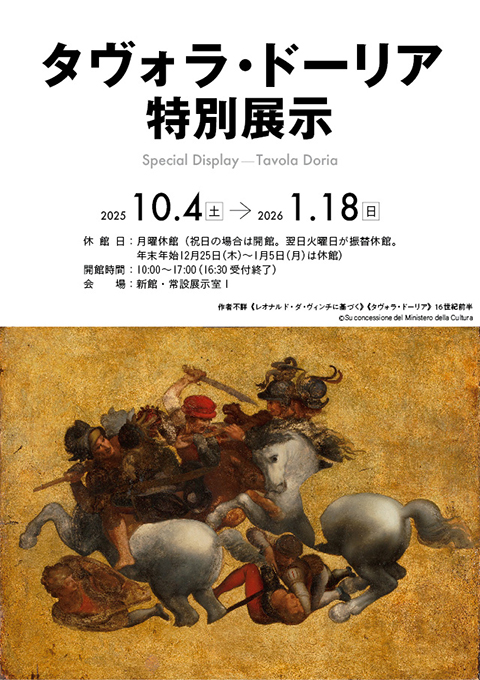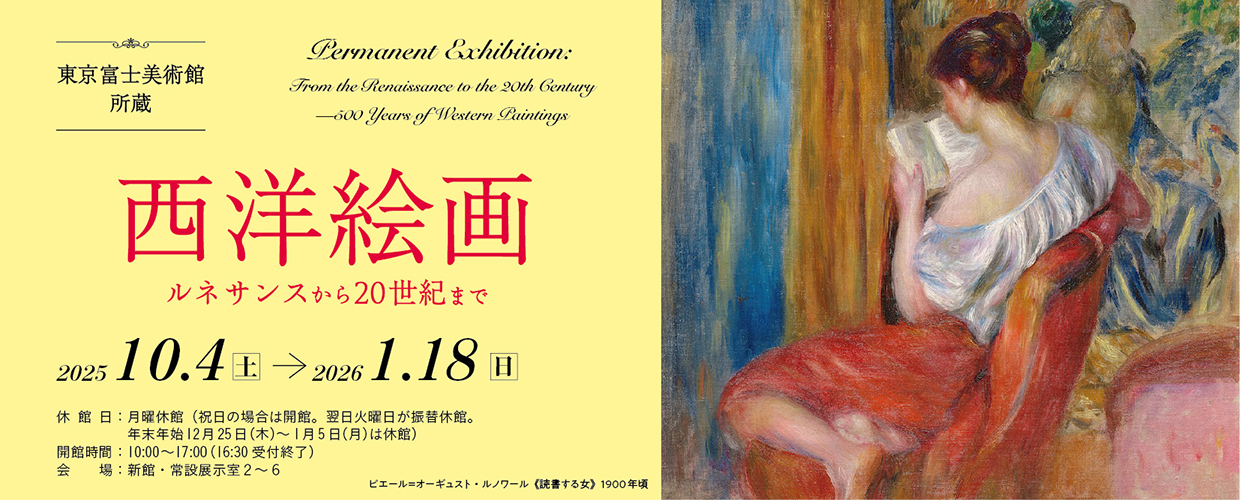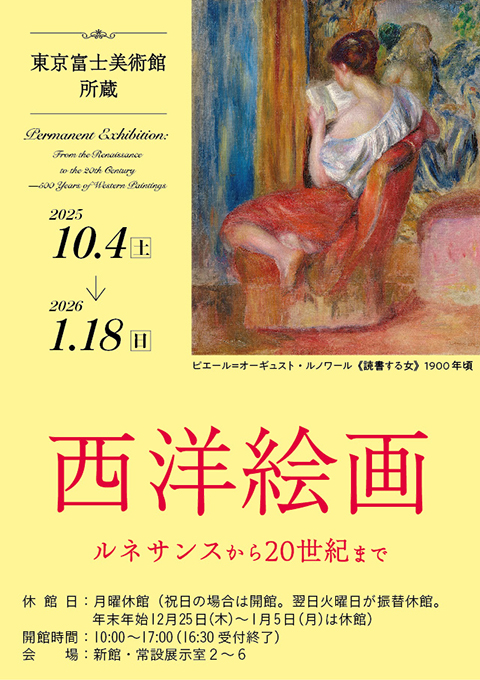文政12年(1829)/絹本着色 軸装(双幅)
114.0×42.3cm(各)
SUMMARY作品解説
織田瑟々は江戸後期の女流画家。本名は政江。画名の瑟々は風の吹く様を意味する。近江国(現在の滋賀県)に、織田信長の九男織田信貞の末裔の娘として生まれる。桜花画で名を馳せた同じく女流画家の三熊露香(ろこう)に学び、17歳の頃には画壇デビューした。露香に師事したのは約2年と短かったが、露香の兄の三熊花顛(かてん)亡き後、桜画継承者として活躍する。晩年は尼僧画家として桜の絵を描き続けた。瑟々が桜の絵を描いていると鳥が実物と間違え、その絵の桜に止まりに来たとの逸話も残されている。本作は左軸の落款により文政12年(1829)、50歳の最晩年作であることが知られる。右軸には墨田川沿いに咲く二種類の桜の若木を、左軸には右軸と同様に盛り上った地面から生える若木と成木を描く。左軸の桜は幹が屈曲し大胆に画面をはみ出して天に向かって伸びて行くような勢いと生命力にあふれている。瑟々の画風が円熟した時期の繊細で優美な作品である。
ARTIST作家解説
織田瑟々
Oda Shitsushitsu1779-1832
近江国(現在の滋賀県)に生まれる。名は政江。父方の先祖は織田信長の九男信貞とされている。画は三熊露香に学び、17歳の頃には画家として成り、三熊思考亡き後、桜画継承者として活躍する。露香とともに女流画家として将来を嘱望されていたが、師露香が没すると10年ほど消息をたつ。一時期京都に出て作画活動をしていたが、最終的には故郷に戻り、仏門に入る。画壇とは無縁の尼僧画家として後世を過ごした。53歳で没。
同じ作家の作品一覧
INFORMATION作品情報

2018年10月6日 (土)~2月10日 (日)
花の礼賛 四大美術館連合大展 国立台湾美術館(台湾、台中)