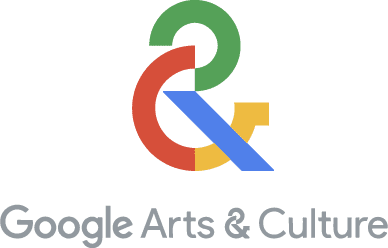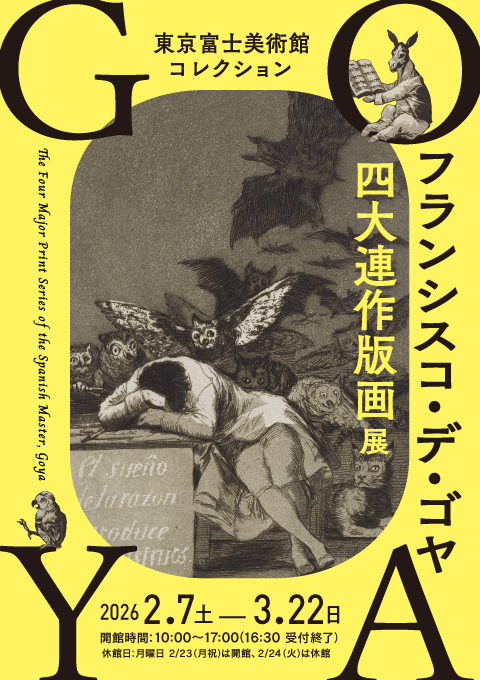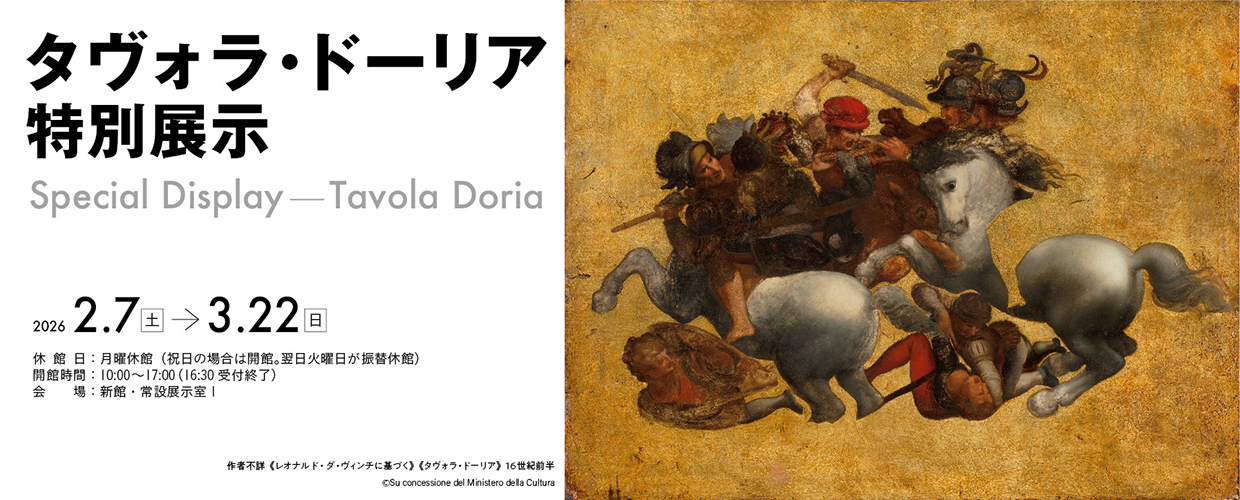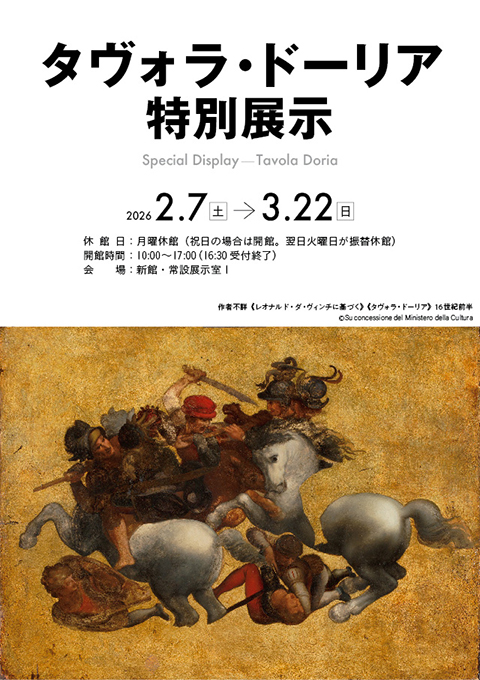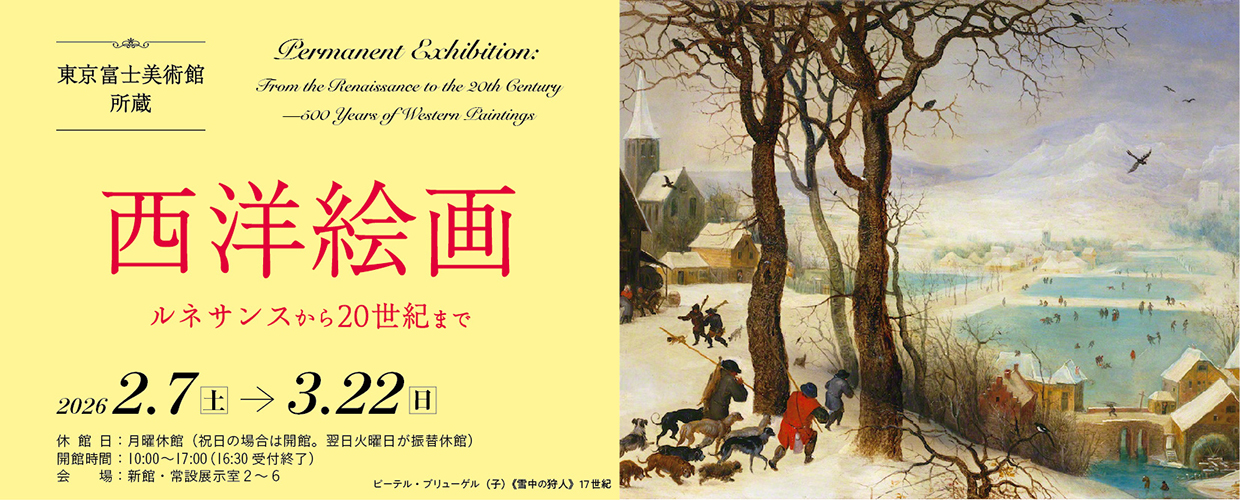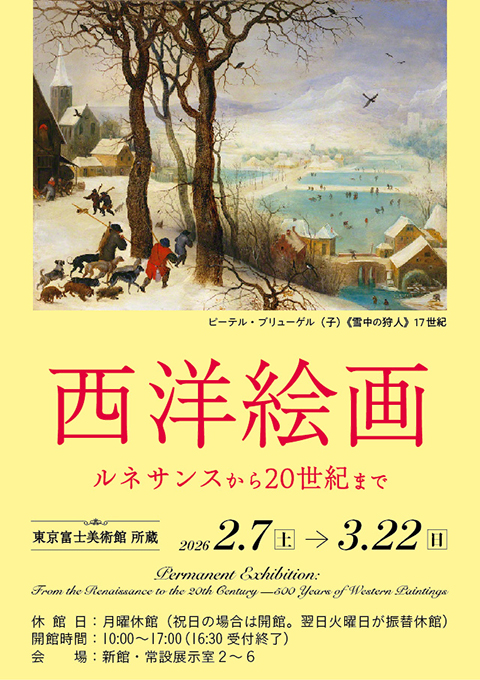清・乾隆年間(1736-95)/
高44.0cm、口径16.0cm、胴径36.5cm、底径24.5cm
SUMMARY作品解説
下膨れの胴部に双耳が付く、商周時代の青銅器の壺を模した壺。粉彩は、ヨーロッパの無線七宝の技術を取り入れて開発された、五彩に比べ微妙なグラデーションが表現できる彩画技法で、康煕年間(1662~1722)に始まる。この作品は、器面全面にそびえる山々を背景に、鹿が木々の間を自由に群れ遊ぶ百鹿図が、風景画のごとく描かれている。「鹿」は、「禄」と通音する吉祥図案。底裏には、2字3行の篆書の青花銘。
ARTIST作家解説
景徳鎮窯
Jing-de-zhen Ware
五代時代から今も続く窯。窯跡は、江西省景徳鎮市一帯に分布。五代時代には、青磁・白磁が作られ、長江以南で発見されている最古の白磁窯。北宋時代には、いわゆる青白磁を完成させる。元時代には白磁が主流となる。元時代後期には青花磁器を生み出し、以後中国を代表する窯業地に発展。明時代には「御器廠」と呼ばれる官窯が置かれ、青花磁器とともに本格的な五彩磁器も作られるようになる。清時代には、粉彩磁器が開発された。なお、明時代後期から清時代前期には、民窯で青花磁器(芙蓉手・古染付・祥瑞)、五彩磁器(天啓赤絵・色絵祥瑞)など多種多様な磁器が生産され、ヨーロッパをはじめ各地に輸出された。
同じ作家の作品一覧
INFORMATION作品情報

2012年9月8日 (土)~11月25日 (日)
中国陶磁名品展 兵庫陶芸美術館(兵庫、篠山市)
1992年5月23日 (土)~6月28日 (日)
清朝工芸の美 秀麗な清朝陶磁を中心に 大阪市立美術館(大阪、大阪市)