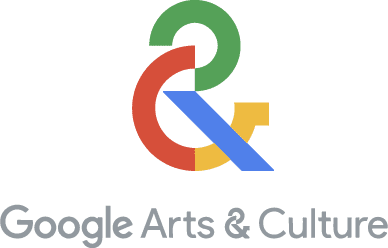北宋(11世紀)/
高21.6cm、口径8.7cm、胴径12.7cm、底径7.2cm
SUMMARY作品解説
磁州窯では、鉄分を多く含む灰色の素地に白化粧をし、透明釉を掛けて焼成するのが基本で、この技術から派生して様々な装飾技法が生み出された。この作品は、なで肩で丸みをもった胴部に、鍔状の口作りを持った瓶である。高台を残して白化粧を施し、その上に鉄釉で五曜文を規則的に配している。点描での文様表現は、磁州窯における鉄絵技法の初期的なもので、後の筆で模様を描く作品より先行するものと考えられている。
ARTIST作家解説
磁州窯系
A Type of Ci-zhou Ware
五代時代末期から近代の窯。窯跡は、河北省邯鄲市に分布。灰色の胎土に白化粧を施し、透明釉をかけて焼成するのが基本的な技法。文様装飾は白無地、白地掻落、白地黒掻落、白地鉄絵、白地紅緑彩、黒釉、翡翠釉など多彩で、器種も豊富。同種の製品を焼造する窯跡は、河北省、北京市、河南省、安徽省、山西省、山東省、陝西省に広く分布し、磁州窯系と総称。北宋時代には白地掻落が出現し、北宋時代末期には白地黒掻落が盛行。金時代以降は、筆彩で文様を表す白地鉄絵などが主流となる。また、同じ頃に作られた、わが国で「宋赤絵」と呼ばれる白地紅緑彩は、複数色の上絵付による文様表現の嚆矢。
同じ作家の作品一覧
INFORMATION作品情報

2012年9月8日 (土)~11月25日 (日)
中国陶磁名品展 兵庫陶芸美術館(兵庫、篠山市)
2002年10月1日 (火)~12月8日 (日)
白と黒の競演 —中国・磁州窯系陶器の世界— 大阪市立美術館(大阪、大阪市)