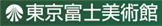カテゴリー
関羽の墓所「関陵」を詣でる
湖北省の当陽は、三国志の物語のなかでも何度も登場する場所で、市内には、趙雲(字は子龍)が劉備の息子を救い出してさっそうと敵をけちらした「長坂坡の戦い」の地や、張飛が何万という曹操軍をたった一人で、橋の上で威嚇して退散させたと伝えられる「長坂橋」など、数々の戦闘やドラマが生まれたところを巡ることができます。
当陽市の中心から西に5キロ離れたところに、関羽の墓所として有名な「関陵」がありました。
「関陵」の門を入ると、境内の所々には、今を盛りと蝋梅(ろうばい)が咲き誇っていました。
古色をおびた赤褐色の建物の壁を背景にした黄色い蝋梅の花は、厳しい寒さのなかで燐とした花が一斉に開き、ふくよかな香りを放っていました。
薄いピンクに発色する梅の花は、高貴な香りと美しさを持っていますが、蝋梅の花が醸し出す風情は、なぜか歴史を感じさせ、古の人々の心や積み重なった出来事、物語を思わせるのでした。
関羽は一武将であるにもかかわらず、この場所は「関陵」と命名されていました。皇帝の陵墓と同格にあつかった「陵」という文字が使われているのは、関羽が亡くなった後、主に仕えるその仁義の篤さが徐々に語り継がれ、とうとう神格化されて「関聖大帝」と呼ばれるようになり、この言葉が使われたようです。
門を入ると拝殿、正殿、寝宮、春秋閣などの建物が並んでいました。
一番奥に位置する「胴塚」は、お椀を被せたような形をしており、塚の上には鬱蒼とした緑の木々が茂っていました。
高さ7メートル、約80メートルの塚の周囲を巡っていると、『三国志演義』の「汜水関の戦い」で華雄を一気に切り倒して凱旋した勇姿や、一度は曹操の軍門に降りながらも、悠々と主の劉備のもとに馳せさんじていく英雄の心意気が、鮮やかな名場面となって甦ってくるのでした。
関羽は、建安24年(219)、呉の呂蒙に自分の砦であった江陵を追われ、撤退していく途中で捉えられ、首をはねられてしまいました。首は、関羽の怨霊に恐れをなした孫権によって、洛陽にいた曹操に届けられ、洛陽の地で手厚く葬られ、後に関林に納められました。一方、首を失った胴体は当陽の地に留まって、この関陵に鎮められたとされています。「関陵」は当時、単なる土の山であったそうですが、時代を経るにしたがって徐々に立派な廟となり、明の時代になって当陽の知県・黄恕(こうじょ)という人が立派な廟を建て、その後も改築をかさねて今日にいたっています。
【トラックバック(0)】
このブログ記事を参照しているブログ一覧: 関羽の墓所「関陵」を詣でる
このブログ記事に対するトラックバックURL: https://www.fujibi.or.jp/assets/files/exhi/3594blog/admin/mt-tb.cgi/131