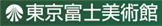カテゴリー
孫権のロマンが宿る「石頭城」へ
南京市博物館で三国時代の素晴らしい青磁器の数々を見学した私たちは、呉の王・孫権がおさめた建業(いまの南京)の西にある砦「石頭城」を訪れました。
南京市西部に位置する、清涼山の上に作られた「石頭城」は、呉の都、建業を守る城としてつくられた城であり、孫権の作戦本部の役割を果たしていました。
水軍によって国をおさめた孫権は、当時、この地形をことのほか気に入り、ここを水軍の根拠地として戦闘の訓練を行いました。当時、「石頭城」の前には、長江が流れており、支流が流入してくるこの河口は大きく広がっており、1000隻にもおよぶ船が停泊することができたといわれています。
石頭城は長江に面した崖を利用して作られた城で、私たちの眼前には赤茶けたレンガと土塁によって建造された明時代の城壁が左右に大きく広がっていました。城の周囲は3.5キロにおよび、高いところでは15.6メートルほどで、城壁の上の方を見上げると突出したところがあり、これが鬼の面のようにみえるところから鬼面城とも呼ばれています。
建安13年(208)孔明は、赤壁の戦いの前夜、蜀と呉との共同戦線を結ぶために呉の地を訪れたという伝説があります。途中、孔明は長江の船の中からこの景観を眺め、船から降りて、馬で石頭山に登りこの地形を観察したとされています。孫権と対面した孔明は、この時の感想をこのように伝えました。「龍(長江)がとぐろを巻き、石(頭)城は 虎 距(うずくま)る、真に帝王の宅です」と。
魏、呉、蜀の三国のなかでもっとも長く続いたのは呉の国でしたが、280年に西晋の将軍・王濬(おうしゅん)によって滅ぼされ、西晋に統一されるまでの間、この城では多くの事件が起こり、物語の舞台となりました。
後漢の末から100年におよぶ三国時代は、幾多の英雄・武将が群雄割拠し、多くのドラマを生み出しましたが、「石頭城」の陥落によって、次の新しい時代をむかえることになるのです。
呉の王・孫権は、建業が亡びる前の約30年前にすでに亡くなっていましたので、この凄惨な都の姿をみることはありませんでした。現在では南京市、東の郊外「梅花山」に孫権の陵墓があり、多くの市民の憩いの場となり、南京を訪れる旅行者の観光スポットとなっています。
【トラックバック(0)】
このブログ記事を参照しているブログ一覧: 孫権のロマンが宿る「石頭城」へ
このブログ記事に対するトラックバックURL: https://www.fujibi.or.jp/assets/files/exhi/3594blog/admin/mt-tb.cgi/109