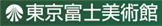カテゴリー
蜀の都・成都
劉備が建国し孔明が治めた蜀の国、その広大な国土のほとんどは標高3000メートルを越える険しい山々に囲まれ、峻厳な地形をはうようにして長江が東へ東へと流れています。今もこの地を訪れる人は、1800年という時を越えて、三国の古き時代を体感し、その興亡が織りなされた旧跡に立ち、様々な思いを巡らすことができるのです。
当時、蜀の都・成都に入るためには、険難の峰を幾重にも越えなければなりませんでした。しかしこの都に入れば、気候も温暖で豊かな農産物に恵まれた「天府」とよばれる別天地でした。
私たち三国志調査団は、昨年の11月、錦秋の季節にこの都を訪れました。
空港に私たちが到着すると、四川省文物管理局のリー・ペイさんが笑顔で出迎えてくれました。
早速、リー・ペイさんの案内で空港から街の中心のホテルへ向かいましたが、車窓からは建設途中のビルや賑やかな商店街がひろがっており、農産物などの物資にも恵まれとても活気に満ちていました。ここの気候は一年を通じて温暖で花曇りのような日が多いといわれています。そのせいか日本のように湿潤で緑が多く、しっとりとした豊かさが伝わってきました。
成都を訪れる人は、必ずといっていいほど劉備と孔明を祀る、武侯祠(ぶこうし)を尋ねます。翌朝、朝の冷気のなかを私たちも武侯祠に向かいました。
「漢昭烈廟」と書かれた壮大な門をくぐると、そこは森閑とした木立に包まれた静かなたたずまいがひろがっていました。 左右には6基の石碑があり「三絶の碑」といわれる孔明の功績をたたえる碑文が最も堂々としていました。さらに進むと中庭をはさんで回廊があり、右に文官の像、左には趙雲(ちょううん)を筆頭におなじみの蜀の武人たちの像がならんでいました。
さらに奥へ進むと正殿には高さ3メートルにおよぶ劉備の像が祀られていました。
孔明の像はさらに奥の正殿に祀られており、羽扇を右手に持ち、ゆったりとした衣服に身を包んだ荘厳な姿の孔明をみることができました。
孔明の像をみたあと、武侯祠から「恵陵」へと向かう小径はとても風情がありました。右側には「恵陵」を取り囲む温かな赤茶色に発色する土塀、左側には「武侯祠」の古風な壁がつづいていました。塀の上には青々とした竹が伸び、さわやかな風が吹き抜けていました。
唐時代の詩聖・杜甫は、この武侯祠の近くに草堂を築いて三年間暮らし、たびたびここを訪れて詩を詠んだといわれています。 「蜀相」とよばれる詩には、孔明を深く敬愛する思いを込めて、次のように歌い始めています。「丞相の祀堂 何れの処にか尋ねん 錦官城外 柏 森々たり・・・」と。
清貧の大詩人が暮らした「杜甫草堂」を後にするときは、もうとっぷりと日が暮れていました。あわただしい成都での一日でしたが、ここを訪れたことで、私はなにか静かに満たされるような心の安堵感を覚えました。「三国志展」に展示するものを必死になって物色しているような、余裕のない貧しい私の心を、緑に包まれた武侯祠の伽藍が醸しだす深い韻律のような調べのなかで、詩人の豊かな魂がいつのまにか私を包み込み、癒してくれていたのかもしれません。
【トラックバック(0)】
このブログ記事を参照しているブログ一覧: 蜀の都・成都
このブログ記事に対するトラックバックURL: https://www.fujibi.or.jp/assets/files/exhi/3594blog/admin/mt-tb.cgi/52