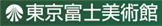カテゴリー
長江を下り三峡を巡る 1
中国の悠久の歴史と文化を生み出してきた母なる河、長江(揚子江)。
いつかゆっくりと巡り、その滔々と流れる河の様子を体感してみたいと思っていました。
本年1月14日、とうとうその願いが叶う日がやってきました。
中国大陸の西の方に位置する重慶市から、約600キロメートルにわたって揚子江の「三峡」を下る船上ツアーで、三国志ゆかりの「白帝城」や「張飛廟」などを巡りながらの3泊4日の船旅でした。
夜、重慶市内のレストランで郷土料理の温かい火鍋をしっかり食べたあと、船に乗り込みました。設備の整った客船は快適な船の旅を楽しめるのですが、私たちが調査する「三国志」ゆかりの場所には止まらないため、あえて真冬の寒さに耐えることを覚悟の上で、質素な二等客船に乗り込みました。

船室に入ってみると案の定、暖房はなく冷蔵庫の中にいるような底冷えのする寒さでした。おもわず船室に備えられたベッドにオーバーを着たまま入りこみ、マフラーを巻き毛糸の帽子を被ってもまだ寒くてどうしようもありませんでした。しかし、「しまった!」と後悔した時には、すでに船はゆるやかに4日間の旅のスタートをきっていました。
しばらくすると重慶の街の灯りが視界から消えて、村々の小さな灯りが見えてきました。そのうちに人工の光りは全くなくなり、満天にひろがる星空と暗い川面、かすかに見える山々のシルエットだけの世界になりました。「ああいま、中国大陸の奥深く、長江の上で眠りにつくんだ」と、何か感慨無量の思いでした。
夜中、船室を出て甲板にたって静かなさざ波の音を聞きながら川面をみつめると、そこには得体のしれない怪物が住んでいて河底に引きずり込まれるような恐怖を覚えました。 翌朝、太陽の光りが差し込んでくると周囲の岸壁はたとえようもないほどの壮大さを表し、幾重にも変化する自然の織りなす姿にいつのまにか釘づけになり魅せられていました。
長江はチベット高原を源とする全長6300キロメートルにおよぶ中国最長の大河ですが、最大の難所が「三峡」と呼ばれています。この峡谷はこれまでに見たことのないほどに雄大で険しく厳しい冬の美しさに満ちていました。ゆっくりとカーブを描きながら進む川岸の風景と両側にそそり立つ山々の風景は、大自然が織りなす雄大な景観の美しさに満ち、三国光芒の歴史のドラマがあり大いなる詩がありました。
乗船した夜は寒さに体が慣れず、ほとんど一睡もできないまま朝をむかえてしまいましたが、翌朝7時には予定通り船は豊都の「鬼城」に到着しました。古寺を巡ったあと船に戻りやっと朝食をとったのですが、中華料理の米や大豆などの素材をそのまま生かした素朴な料理には、しみじみと大陸の味がしてくるのでした。 再び、船はゆるやかに下流へとむかいました。太陽の光線がまぶしいほどに輝いてきました。船室から外に出て川岸からそそり立つ雄大な山々や、行く手にひろがる雄大な風景をビデオや写真におさめました。
再び、船はゆるやかに下流へとむかいました。太陽の光線がまぶしいほどに輝いてきました。船室から外に出て川岸からそそり立つ雄大な山々や、行く手にひろがる雄大な風景をビデオや写真におさめました。 船内の生活は、あまりにも時がゆったりと流れていくため、次第に日常の生活感覚がなくなっていくようでした。10時間あまり経ち、再び二日目の夜を迎える頃、周囲の山々が次第に険しくなってきていることが分かりました。
午後9時30分に雲陽の「張飛廟」に到着。ここは張飛の魂を鎮めるお墓で、多くの張飛のファンが訪れるところです。
張飛は、221年に義兄弟の関羽の弔い合戦のために呉にむけて出発する前夜、部下に恨まれて寝首をかかれてしまいます。

張飛廟に伝えられる伝承では、張飛を暗殺した部下の張達らは、船で長江を下り呉の孫権のもとへ首を持参しようとしたのですが、運ばれていく途中、張飛の首が何かのひょうしで長江に落ちたと伝えています。死しても劉備を慕う張飛の首はそのまま逆流して蜀の国へ向かって流れていったそうです。雲陽まで流れていったところ、土地に住む年老いた漁師によって拾われ、その後丁重に「張飛廟」に葬られたというのです。
「張飛廟」を見学して船に戻ったのは、すでに午前0時に差しかかっていました。今夜も眠れぬまま夜空を眺めながら過ごすことになるのでしょうか。
いよいよ明日の朝には「白帝城」を仰ぎ見ることができるでしょう。
【トラックバック(0)】
このブログ記事を参照しているブログ一覧: 長江を下り三峡を巡る 1
このブログ記事に対するトラックバックURL: https://www.fujibi.or.jp/assets/files/exhi/3594blog/admin/mt-tb.cgi/62