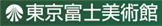カテゴリー
書画をたしなんだ張飛?
張飛の一世一代の晴れ舞台は、当陽での「長阪の戦い」ですね。主君の劉備を追撃する曹操の軍5千騎を前にして、張飛の軍は20騎。どうみても勝ち目のない戦いですが、長阪の橋の上に立って、目をいからせ矛を横たえた張飛は「我は張益徳なり、死を覚悟で我に挑む者はないか」と一喝。三国志演義では、そのあまりの迫力に曹操の側にいた夏侯傑が馬から転げ落ち、これを期に全軍が総崩れになったと記しています。芝居ではこの一喝で橋が崩れ落ち、川の水も逆流しはじめたとされています。張飛の豪傑ぶりは、後世の物語や芝居のなかで多いに脚色され、三国志の登場人物のなかでも人気の高いキャラクターになっています。

さて向かうところ敵なしの剛勇無双の張飛ですが、若い頃に書画を学び、かなりの芸域に達していたとする説があることをご存知でしょうか。小さい頃から気性が激しく気宇壮大な気風をもっていた少年をみた王養年という名の伯父が、将来の大成のために書や絵画をたしなみ、広く書物を読むことを教えたと言われています。文武両道で生きることの大切さを学んだ張飛は、短期間で書画をマスターしたようで、今も故郷の州などのゆかりの地に、独自の風格をもった書や絵画が碑文や壁画となって残っているそうです。
張飛の墓のある廟は、劉備の生まれた楼桑村から2キロほど北の張飛店とよばれる集落のなかにありますが、張飛廟を取り囲む紅殻色の塀を背景にして、バラが一斉に咲いていました。
【トラックバック(0)】
このブログ記事を参照しているブログ一覧: 書画をたしなんだ張飛?
このブログ記事に対するトラックバックURL: https://www.fujibi.or.jp/assets/files/exhi/3594blog/admin/mt-tb.cgi/142