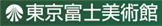カテゴリー
孔明終焉の地—五丈原
隋・唐の爛熟した文化の面影を残す西安に着いて、陝西歴史博物館や碑林博物館などの見学に時間をかけた翌日。私たち調査団は、とうとう諸葛孔明の終焉の地、五丈原を訪ねることになりました。西安から約70キロ余りの道のりを車で約一時間ほど走ると、うっすらと靄がかかった前方に、それほど高くない丘陵のような台地が見えてきました。
関中平原の西側に位置する五丈原は、南北5km、東西2kmの台地で、渭水の河岸からせり上がった最も高いところで120m。その全容を眺めるとなだらかな台地をもつ半島のような形をしていました。
台地の上にあがると、原っぱ一面に小麦が植えられ、そこが台地の上である事を忘れてしまうほどでした。
広々とした小麦畑の真ん中に一本の道が通っていました。
この台地は上からみると琵琶のような形になっており、広々とした北側から南へ移動していくと徐々に細くなっていき、最も細くくびれたところに昔の土塁の跡が残っていました。
このあたりの幅が五丈(約12m)であることから、五丈原と名付けられ、諸葛孔明の大本営の地であったとされています。
孔明は、234年の春、魏を打つために6度目の北伐を行いました。蜀軍10万の兵を率いて漢中を出発し、険しい秦嶺山脈を越えて漢中平原に向かいました。
4月には渭水の南岸にあたる五丈原に到着し、ここに陣を張りました。
一方、魏の司馬懿は30万の軍とともに渭水の北岸に到達し、孔明と向き合いました。戦いは長期戦となり、孔明はこの台地を利用して屯田を行い、軍の兵糧を確保し司馬懿に攻撃をしかけます。しかし、持久戦にもちこめば勝てると信じた司馬懿は動かず、孔明は徐々に追い込まれていきました。八月(今の10月初め)、五丈原に秋風が吹くころになると、孔明は自分の身に死が訪れつつあることを悟らざるを得ませんでした。戦い半ばにして孔明は54歳で亡くなります。
孔明の臨終に符合して、大きな星が東北より西南に流れ、蜀軍の本陣に落ちたと言い伝えられていますが、『三国志演義』では、星が落ちるのを見た司馬懿は、「孔明が死んだ」と直感し一気に総攻撃を開始します。しかし、孔明の木像をすえて迎え撃つ蜀軍の姿に、司馬懿は恐れを抱き、逃走する場面が記されています。
後事の一切を諸将に託した孔明は遺体となって五丈原を降り、漢中の定軍山に葬られました。
6度にわたる孔明の北伐は、いずれも失敗に終わり、志半ばにして死を迎えなければならなかった孔明の思いは、どのようなものであったのか---------。
五丈原を吹き抜ける風を受けながら、私たちは、展覧会のなかで五丈原のもつ意味が徐々に大きくなっていくことを予感していました。
魏、呉、蜀の三国志の舞台を巡ってきた私たちの旅も、今回の「五丈原」を区切りにさせていただきます。拙い文章を読んでいただき、私たちが撮影してきた写真を見てくださったことに心から感謝致します。
次回からは、三国志調査の旅で撮影してきた思い出のスナップや風景、文物などに、短いエッセーをつけた「三国志フォトエッセー」として、新たにスタートさせていただきます。ひきつづき三国志の舞台をご一緒させていただき、三国志の魅力を味わう場となれば嬉しいです。
【トラックバック(0)】
このブログ記事を参照しているブログ一覧: 孔明終焉の地—五丈原
このブログ記事に対するトラックバックURL: https://www.fujibi.or.jp/assets/files/exhi/3594blog/admin/mt-tb.cgi/136