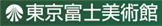カテゴリー
孫権の都・建業(南京)へ
これまでは、主に蜀と魏の国を巡ってきましたが、今回は呉の地を訪れることにしましょう。
呉の孫権は、正式に皇帝に即位した年(229年)の秋に、建業(いまの南京)を呉の都と定めました。南京市内には、南京博物院をはじめ、南京市博物館、太平天国歴史博物館などのすばらしい博物館があり、三国時代の文物や資料に出会う事ができます。また、孫権の砦として使われた「石頭城」や、紫金山内にある孫権の墓(孫権墓)を散策すると、1800年前の昔にタイムスリップして、当時をしのぶことができるのです。
南京市博物館をおとずれた私たちは、白館長の案内で三国時代の素晴らしい青磁の名品の数々に出会う事ができました。この博物館のコレクションの代表格は、なんといっても、三国時代に焼成された青磁の名品群で、薄い青緑色に発色した磁器の花瓶、壷などからは、制作した陶工や当時の人々の、素朴で人間的な心のぬくもりが伝わってくるのです。
三国時代の文物というと、戦乱の時代を特徴づけるような、男性的で質実剛健な造形やデザインを想像していたのですが、意外にも、この時代に生み出された陶磁器の作品をみていくと、やさしくほのぼのとした人間的な温かさに溢れた作品が多いことに気づきました。
「大三国志展」には、この博物館から14点の文物・資料が出品されますが、そのなかでも、私が特に気に入っている作品は、次に紹介する2点の青磁です。一つは「青磁堆塑人物缶」という作品です。
副葬品として作られたもので、難しい題名がついていますが、わかりやすく言えば壷の上に人物や動物、鳥などをぎっしりと積み上げるようにして形作った壷という意味になります。壷の上部には楼閣が作られ、その周囲や建物のなかに鳥や羊、人間、仏像などがあらわされています。それらの表現は、表面的には、決して技術の冴えを見せるようなものではありませんが、動物も鳥も、人間も仏様も全てが平等にあつかわれ、壷全体からはつらつとした生命観が伝わってきました。作られてからすでに1800年も歴史を刻んでいるのですが、エネルギーに満ちた豊かな生命の固まりのよう感じられてなりませんでした。
二つ目の作品は、「青磁羊」です。

この作品は、形の複雑さはなく、足を折り曲げて四つん這いになっている羊が、実に素朴でシンプルに表現されています。しかしよく見ていくと、単純な形と色彩のなかに、見る人を安堵させるような、平和な心にいざなうような作者の思いが、この造形のなかに込められているのが感じられます。青磁の発色は非常に繊細で、頭から首、胴体にかけてすばらしい中間トーンの変化をみせています。私もこれまでに、いくつかの青磁をみてきましたが、これほどに温かな印象を与えてくれるものは無かったように思います。これを制作した陶工の豊かな感性とともに、完璧な製陶技術の見事さに脱帽してしまいました。
この二つの作品は、国家一級文物(日本でいう国宝)に指定されており、中国を代表するこの時代の名品といってよいと思います。
三国の英雄たちが群雄割拠する戦乱の時代のなかにあっても、こうした名品を生み出す事のできる文化の高さ、精神性の高さが、時代の根底にきちんと存在していたことを、これらの作品を通して知る事ができるのです。
次のブログでは、南京市内にある孫権の砦「石頭城」をご案内します。
【トラックバック(0)】
このブログ記事を参照しているブログ一覧: 孫権の都・建業(南京)へ
このブログ記事に対するトラックバックURL: https://www.fujibi.or.jp/assets/files/exhi/3594blog/admin/mt-tb.cgi/99