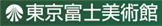カテゴリー
三顧の礼---[古隆中]を訪れる
三国志の物語には個性あふれる英雄豪傑が次から次へと登場してきます。それぞれの英傑たちの生き様が幾重にも展開されるこの物語には、何度読んでも新たな驚きや発見があり、今を生きる私たちに多くのことを教えてくれるのです。
この時代、漢王朝の基盤が崩れ去り世相が乱れていくなか、民衆は新しい時代が到来することを望んでいました。すでに新しい時代への胎動が始まっていました。この時代は人の心を沸き立たせてやまない不思議な魅力と緊張にみちていました。未来を担う青年たちの心を引きつけ、やむにやまれず行動へと駆り立てていくような時代でもあったのです。
私たちの3回にわたった調査では、約70カ所にのぼる三国志ゆかりの史跡や博物館などを訪れましたが、どの場所へ行っても私は中国の関係者に、「一番好きな登場人物は誰ですか?」と聞くことにしていました。地域によって好き嫌いの差はありましたが、そのなかでもやはり孔明の人気は群を抜いて高く、地域をこえ時代をこえて孔明の知謀や人徳が評価されていることを知りました。
孔明の幼少時代から青年時代については、それほど詳しい記録がないそうです。しかし、三国志を愛し孔明を知る人にとっては、孔明が青年時代をどのように生きたのか、どのようにしてその優れた天分が磨かれていったのか。そして孔明が登場するきっかけとなった[古隆中(こりゅうちゅう)]がどのような場所だったのか。きっと興味が尽きないことと思います。
私たちは昨年の1月下旬、三峡の調査行を終えたあと、赤壁の地にむかう途中に湖北省の[古隆中]を訪れました。
襄樊(じょうはん)市から車で13キロほど走ると、うっそうと繁る樹木の向うに隆起した山が近づいてきました。
[隆中山]と呼ばれるこの山麓で、孔明は17歳から27歳の10年間、書に親しみ、あるときは詩を吟じ、時代の行く末に思索を重ねていました。
また、ここを拠点として優れた人物を求めて様々な地方に赴き、未来を語り多くの情報を集めたといわれています。
この時期すでに孔明の名は、周囲の知るところとなっていました。また、孔明自身も自己の使命を全うするために、仕えるべき人は誰なのかを心の奥底で求め続けていました。
一方、劉備はすでに47歳になっていましたが、いまだに漢室再興への思いを果たすことができず、不遇の日々を送っていました。そうした劉備のもとに伏龍とよばれる優れた人物がいることが知らされました。劉備は未来の大成のため20歳下の孔明に会うために、3度にわたってこの[古隆中]に出向きました。劉備が真の逸材を得るために3度礼をふんだことを、後に[三顧の礼]とよんでいますが、『三国志演義』では、このとき孔明は未来への大いなる指針を劉備に語ったと伝えています。孔明はこの日を期して、劉備を主と仰ぎその理想を実現するために全身全霊をつくしていきます。弱小軍団の将であった劉備はやがて、成都を中心とする広大な蜀(益州)の主となり、孔明の言葉通り[天下三分の大計]、魏・呉・蜀の三国鼎立の時代が到来するのです。
[古隆中]は、明の時代になって孔明の威徳をしのんで整備されました。
境内には劉備が関羽と張飛を伴って訪れたときに通った[小虹橋]や[三顧堂]
、劉備が馬を繋いだとされる柏の巨木がそびえ立っていました。中に入ると郭沫若の扁額をかけた[諸葛草廬]が古色をおびた風情をつたえていました。
三度目にここを訪問した劉備は、草廬で昼寝をしている孔明を起こさないように気遣い、眠りがとけるのを待ったと言われています。このような山懐に抱かれた静かなところから、時代は大きく未来にむかって回転を始めたのです。
「大三国志展」では、孔明を描いた絵画が5点出品されます。なかでも故宮博物院が所蔵する明時代の宣徳帝によって描かれた作品は、品格に満ちた作品で、孔明が竹林のなかで横になって悠々と思索している姿が描かれています。また、最晩年の戦い[五丈原]で車駕に乗って指揮をとる孔明を描いた「秋風五丈原」。
[古隆中]の題材では、雪が降りしきるなか孔明を求めて古隆中へ向かう劉備、関羽、張飛の主従を描いた大画面の屏風などが公開される予定です。
【トラックバック(0)】
このブログ記事を参照しているブログ一覧: 三顧の礼---[古隆中]を訪れる
このブログ記事に対するトラックバックURL: https://www.fujibi.or.jp/assets/files/exhi/3594blog/admin/mt-tb.cgi/81