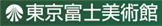カテゴリー
赤壁の古戦場に立つ
赤壁市の博物館をあとにして、見渡す限りつづく畑の中を車で30分ほど走ると、やがて前方に長江が見えてきました。
赤壁の古戦場は長江の南岸にあり、ここから曹操が陣取った北岸の方向を眺めると、長江の川幅は広く海とも思われるような雄大な景色が広がっていました。
古来から「赤壁の地」とされていた場所は、5から7箇所もあったとされています。日本の邪馬台国論議のように様々な説があげられ、発掘品や文献を調査していった結果、いま私たちがたどり着いた湖北省赤壁市の旧蒲圻(ほき)に位置するこの場所に確定したそうです。
車をおりて岸辺にひろがる村落を歩いてみました。
質素な家々が並び、道ばたでは多くの人々が仕事をしたり談笑していました。どの人も素朴で健康的な親しみのある顔の表情でした。舗装されていないほこりにまみれた道路と家々の間には1mを超えるほどの大きな魚が無造作にずらりと並べられ、天日干しされていました。
家々の軒からも大小様々な魚がぶら下がっていました。
私たちは地元の方に案内されるままに一軒の食堂に入り昼食をとることにしました。出された鍋のなかには、さっき通りでみたあの大きな魚が大胆にぶつ切りにされ調理されていました。原始的でエネルギーの源のような料理。料理を食べているのは私たちではなく、料理の方が私を飲み込んでしまうような迫力のある料理。中国にきてはじめてこのような原始的で野性的な料理と出会いました。
「赤壁古戦場」の地は、現在、広大な史跡公園のようになっており、目的の赤壁山に着くまでの間に様々な建物や庭園を眺めながら、長江側からみて背後から迂回して近づいていくようになっていました。
赤壁山に登る手前の公園の中心には、兜をかぶりマントを翻らせている6メートルを超える大きな「周瑜(しゅうゆ)」の像がたっていました。また南屏山の「武候宮(ぶこうきゅう)」には「拝風台(はいふうだい)」の額がかかげられており、孔明が火攻めの作戦を成功させるために東南の風が吹くことを祈ったとされる場所をしのぶことができました。
赤壁山に登ると「翼江亭(よくこうてい)」という名の六角形の東屋(あずまや)があり、そこからは長江が真下に眺められる絶景の地となっていました。この場所は巨大な曹操軍に対峙して戦いにのぞんだ呉軍の総司令官「周瑜」が全軍の指揮をとったところと伝えられています。
対岸に陣をはった曹操は、武人であると同時に偉大な詩人でもありました。
「三国志演義」によれば曹操は、呉軍との大決戦を前にして長江の岸に自ら立って「短歌行」をつくり吟じたと伝えられています。
また、対する「周瑜」は、呉軍きっての美顔の武将でしたが、楽器の名手でもあったと伝えられています。私の勝手な想像を許していただければ、戦いを前にして武者震いをおさえながら、ここで得意の楽器を鳴らしたのかもしれませんね。
やっとたどり着いたという思いで赤壁山の頂上に立ち、高揚する心を抑えながら眼下を見下ろすと、悠然と長江が流れ、数キロ先とも見えるはるか向うの対岸には森林のように緑が茂っていました。
当時、曹操の20万におよぶ大船団が南岸をにらんで対峙したこの場所は[烏林]ともよばれていました。『演義』では、曹操の大船団は[連環の計]によって火攻めにあい、兵士たちの船酔いを防ぐためにがっちりと繋がれた船は、次々と燃えひろがっていきました。この時の天を焦がすほどの火炎によって対岸の岩壁が真っ赤に染まったため、この地に赤壁という名が付けられたとされています。
岩壁の上から降りていくと岩肌には、[赤壁]の二文字が鮮やかに彫られていました。
岩の色はまさしく赤茶色で全体が赤く発色していました。
今から1800年前の西暦208年、この戦いで魏の曹操が大敗北することによって、孔明が予見した通り、魏、呉、蜀の三国鼎立の時代に入っていくのです。
【トラックバック(0)】
このブログ記事を参照しているブログ一覧: 赤壁の古戦場に立つ
このブログ記事に対するトラックバックURL: https://www.fujibi.or.jp/assets/files/exhi/3594blog/admin/mt-tb.cgi/76