カテゴリー
諸葛孔明の指導者学(3−2)
ただ、渡辺精一氏も述べておられるように、廖立の「意見」にはそれなりに筋が通っている面がある。特に関羽が突進していって敗れたことは否定できない。廖立の思い上がりもあったであろうが、単なる恨みや妬みから発生した批判ではないことも確かなのである。それなりに筋が通っていたからこそ罰せられたという部分もあったろうし、逆に死刑にもならなかったと見ることもできる。孔明としては、北伐という大目的に向けて団結しなければならないときに、高位にあるものが軽々しく自らの所属する組織(この場合は蜀漢の政府)を批判するのは避けなければならないと判断したとのであろう(この段落については、渡辺精一〔著〕『諸葛孔明の組織改革 [三国志]に学ぶリストラ』(PHP研究所 1994年)207〜212頁参照)。
その彼もまた、孔明が亡くなったと聞くと、涙を流して「私は蛮族になってしまうだろう」と述べたという。蜀漢の滅亡を予期したためであろうか(宮川尚志〔著〕『諸葛孔明—「三國志」とその時代—』(光風社出版 1984年,もとは冨山房 1940年,桃源社 1966年)205〜206頁参照)、それとも自らの復活の可能性が無くなったと考えたからだろうか。
李厳・廖立の二人に共通していることは、自らに対する処罰という孔明の人事に対して怨みを抱いていないということである。これは、孔明が公正に法を用い、公平な人事を心がけていたということを示しているのであろう。
また、孔明はこのような二人をなんとか生かそうと努力してきたフシがある。特に李厳については、はっきりとその努力の様子が『三国志』に記載されている。できる限り、その人材の長所を「よきところよきところ」という思いで見つめながら、北伐という大目的のために配慮してきたのである。そのような孔明の人材に対する姿勢も学ぶべきであろう。
【トラックバック(0)】
このブログ記事を参照しているブログ一覧: 諸葛孔明の指導者学(3−2)
このブログ記事に対するトラックバックURL: https://www.fujibi.or.jp/assets/files/exhi/3594blog/admin/mt-tb.cgi/104
【コメント(1)】
【コメントする】
※入力されたメールアドレスは記事に反映されず、ブログの管理者のみが参照できます。
※URLの入力は必須ではありません。
※なお、送られたコメントはブログの管理者が確認するまで公開されません。

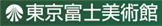

処罰をされて、不満をもたないというのは、本当にすばらしいと思います。
公平・公正もさることながら、孔明の取り組みの真剣さがあったのでしょう。
志(大目的)は、人の思いを超越するのでしょう