カテゴリー
「大三国志展」学術討論会
2009年3月14日14時30分から東京都八王子市の東京富士美術館会議室において「大三国志展」学術討論会が開催されました。
中国からは学術交流団が来日し、「大三国志展」前橋展を観覧していただいただけでなく、14日の「大三国志展」来場者数100万人突破記念セレモニーにも参加していただきました。この学術討論会には、中国側からは学術交流団の羅伯健団長(中国文物交流中心主任)、高大倫先生(四川省考古学研究院院長)、馬宝烈先生(遼寧省博物館館長)、師建民先生(甘粛省博物館)が、日本側からは東京富士美術館の野口満成館長ほか学芸員の方2名と満田が参加しました。
討論会の最初に、野口館長・羅伯健団長からの挨拶があり、その後高大倫先生と馬宝烈先生のご発表がありました。
高先生は「民間三国・文学三国・文献三国・考古三国」と題して発表されました。まず四川大地震による破壊状況を、写真(パワーポイント)を使って紹介していただきましたが、そこでは「地震が起こった地帯が諸葛孔明の北伐ルートと重なる」とのお話もありました。個人的に非常に興味深いご発表でしたので、以下にポイントをまとめておきたいと思います。
●民間伝承における『三国志』については、諸葛鼓(諸葛孔明が軍で使ったとされる銅製の太鼓)や武侯歇馬石(南征軍が休んだとされる場所の崖に宋代に刻まれた文章がある)といった諸葛孔明の南征に関するものを紹介されました。ちなみに、高先生のご実家は諸葛孔明の南征のルート沿いにあるとのことでした。
●さらに、『三国演義』が中国の著名人に与えた影響や陳寿『三国志』の概説があった上で、考古学から見た『三国志』について述べられましたが、「『三国志』を本当に知るには考古学上の成果を学ばねばならない」という趣旨のお話もされていました。
●凉山昭覚三国軍屯遺址を写真で紹介されました。ここは2000年に発見された諸葛亮の南征関連の遺跡で印や土器が出土しているが、ここはまだ発掘されていないとのことでした。筆者にとってはこのお話が一番興味深いものでした。
●四川省考古学研究院は成都武侯祠博物館と協力し、諸葛孔明の南征・北伐に関する遺跡を3年がかりで発掘する計画がありましたが、大地震でストップしているそうです。ただ、計画がなくなったわけではないので、これから再開する努力をしたい、とおっしゃっていました。
●四川の遺跡では墓葬も重要であり、三国時代のものでは楽山麻浩崖墓があり、ここには蜀漢の年号が刻まれているだけでなく、仏像も刻まれているそうです。
●また、最近の中国での「三国熱」のお話もされたが、これには日本からの影響(日本へ行った留学生が日本の小説・漫画『三国志』を持ち帰ったことから始まる)が非常に強いのではないか、との見解をしめされました。
このご発表に対して、満田は考古学上の成果を踏まえた最近の日本での『三国志』研究の状況について大まかな話を少しさせていただきました。
次に馬先生は仇英と彼の≪赤壁図≫に関する概説を、写真(パワーポイント)を使ってお話していただきました。それによりますと、現存する仇英の≪赤壁図≫は、上海博物館のものと2007年にオークションに出てきたもの、そして遼寧省博物館のものと三つあるとのことで、書かれた年代の順はオークション版、上海博物館版、そして遼寧省博物館版であるということでした。
日本側からは、東京富士美術館の学芸員の方が展示の様子をスライドで示しながら、注意した点などをお話しされました。その内容を踏まえた上で、満田が日本での『三国志』に関する研究状況や日本での『三国志』の受容のあり様をお話し、「大三国志展」準備段階での留意点・工夫点について解説させていただきました。
これらの話に対する高氏からの意見として、「大三国志展」のスタッフの皆さんが三国時代の歴史や小説に関する詳しい研究を踏まえた上で、鑑賞者層についても配慮した展示を心がけたことや、展示の前半部分で物語を語る雰囲気を作っていたことなどについて長所として指摘していただきました。
最後に羅先生が大成功の理由として、社会的背景などの様々な要素を考えたテーマの選択がなされたことなどを指摘され、学術的に最先端のものと定着しているものを使い分け、歴史と文学を結びつけて展示されていたことについても述べられました。
結局、予定の時間をかなりオーバーし、熱のこもった議論が交わされました。今回の討論会の内容が、今後の中国の文物の展覧会、ひいては中日友好に生かされれば幸いです。
【トラックバック(0)】
このブログ記事を参照しているブログ一覧: 「大三国志展」学術討論会
このブログ記事に対するトラックバックURL: https://www.fujibi.or.jp/assets/files/exhi/3594blog/admin/mt-tb.cgi/171

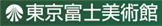

【コメントする】
※入力されたメールアドレスは記事に反映されず、ブログの管理者のみが参照できます。
※URLの入力は必須ではありません。
※なお、送られたコメントはブログの管理者が確認するまで公開されません。