カテゴリー
諸葛孔明の指導者学(2—2)
孔明が罷免した人物—李厳の場合(2)
その後、李厳は自分が孔明に比べて重んじられていないと思ったのか、「地方行政区分を改めて新しく州を作り自分をその長官にしてくれ」と言ったかと思えば、孔明が北伐準備のために李厳を漢中に呼び寄せようとすると「自分も幕府(高位にある者が自分専用に作った役所)を開きたい」と申し出たりしていたが、孔明はそれでも李厳の才能を生かそうとしていろいろと優遇したのである。
しかし、それを裏切るような事件が起こる。231年に孔明が出撃した際に李厳(李平に改名していたが、本論では李厳と表記する)に輸送を監督させていたときに、「食糧輸送がつながらない」として孔明を呼び戻した。孔明が撤退すると、李厳は「輸送はうまくいっているはずなのに、どうして戻ってきたのか」と驚いてみせ、皇帝・劉禅には「退却したふりをして、敵を誘い出すつもりです」などと述べていたのである。孔明は李厳の自筆の手紙を証拠として提出し、李厳は罪を白状して謝罪し、庶民とされて流罪となった。そんな中でも、孔明は李厳の子・李豊には将来の李厳の復活も含めた励ましの手紙を送っている(『三国志』巻40李厳伝裴注所引の孔明の手紙)。
李厳は孔明が亡くなると、病気になり亡くなった。孔明が自分を復活させてくれると期待していたが、孔明の後継者では無理だと思っていたからである。
ちなみに、先ほどの李厳に対する手紙にも表れているように、孔明は少なくとも単なる堅物人間ではなかったようである。『三国志』巻42周伝裴注所引『蜀記』には、それを示すようなエピソードが載っている。陳寿の師であり、蜀漢の大学者として有名な周がはじめて孔明に会った時のこと、その際の周の様子を見て、孔明の左右にいた者はふき出してしまった。『三国志』巻42周伝では、周は風貌が素朴で、性格は誠実で飾り気が無く、当意即妙の弁論の才も無かったとされるので、朴訥としたものがあったのかもしれない。周が退出した後、役人が笑った者の処分を申し出たが、孔明は次のように答えたという。
「私でさえ我慢できなかったのだから、左右の者は仕方ないだろう。」
おそらく「宮廷内で会議などの最中に笑ってはいけない」という規定があったのであろうが、この場合に孔明はその規定を適用しなかったというところからすると、人情の機微というか、物事の加減がわかっていたということになるだろう。
【トラックバック(0)】
このブログ記事を参照しているブログ一覧: 諸葛孔明の指導者学(2—2)
このブログ記事に対するトラックバックURL: https://www.fujibi.or.jp/assets/files/exhi/3594blog/admin/mt-tb.cgi/101

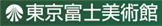

【コメントする】
※入力されたメールアドレスは記事に反映されず、ブログの管理者のみが参照できます。
※URLの入力は必須ではありません。
※なお、送られたコメントはブログの管理者が確認するまで公開されません。