カテゴリー
酒にまつわるエピソード—魏の場合(2)
魏の人物の「酒での失敗」としては、曹植の件も取り上げないわけにはいかないだろう。219年、曹仁が関羽に包囲されると、曹操は曹植に救援するように命じたが、曹植は酔っ払っていて命令を受けることができず、曹操は後悔して命令をとりやめたという(『三国志』巻十九曹植伝)。この話に付されている裴松之注に引用された『魏氏春秋』によると、曹植を酔わせたのは太子であった兄の曹丕だとされるが、にわかには信じがたい。確かに曹丕と曹植は曹操の後継者をめぐって争ってはいたが、すでに後継者は決定した後である。それに石井仁は「後継者問題は曹操が意図的につくりあげた政治状況であったという見方もできる」としている(石井仁『曹操—魏の武帝』(新人物往来社 2000年)226ページ)ことも考えると、この曹植の一件は簡単には評価できないだろう。
実は、禁酒令を出した曹操本人もお酒は大好きだったようで、彼の「短歌行」という詩を見ると、「酒に対しては当に歌うべし 人生幾何ぞ……何を以ってか憂いを解かん 唯だ杜康(酒のこと)有るのみ」などとある。加えて『全三国文』巻一や『斉民要術』巻七・笨麹餅酒第六十六を見ると、曹操が後漢の皇帝に対して「九春酒法」という酒の作り方を上奏していることがわかる。
また、この時代には葡萄酒も飲まれていたことがあるようで、魏の文帝・曹丕は葡萄について述べた詔書の中で「醸すれば酒となるが、……善く酔うけれども醒めやすく、通り過ぎれば涎が流れてきて唾を飲み込んでしまう」と書いており(『太平御覧』巻九七二蒲萄所引「魏文帝詔」など)、非常に興味深い。
実は、禁酒令を出した曹操本人もお酒は大好きだったようで、彼の「短歌行」という詩を見ると、「酒に対しては当に歌うべし 人生幾何ぞ……何を以ってか憂いを解かん 唯だ杜康(酒のこと)有るのみ」などとある。加えて『全三国文』巻一や『斉民要術』巻七・笨麹餅酒第六十六を見ると、曹操が後漢の皇帝に対して「九春酒法」という酒の作り方を上奏していることがわかる。
また、この時代には葡萄酒も飲まれていたことがあるようで、魏の文帝・曹丕は葡萄について述べた詔書の中で「醸すれば酒となるが、……善く酔うけれども醒めやすく、通り過ぎれば涎が流れてきて唾を飲み込んでしまう」と書いており(『太平御覧』巻九七二蒲萄所引「魏文帝詔」など)、非常に興味深い。
【トラックバック(0)】
このブログ記事を参照しているブログ一覧: 酒にまつわるエピソード—魏の場合(2)
このブログ記事に対するトラックバックURL: https://www.fujibi.or.jp/assets/files/exhi/3594blog/admin/mt-tb.cgi/68

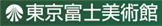

【コメントする】
※入力されたメールアドレスは記事に反映されず、ブログの管理者のみが参照できます。
※URLの入力は必須ではありません。
※なお、送られたコメントはブログの管理者が確認するまで公開されません。