カテゴリー
赤壁の戦いについて(その4終)
『魏志』では曹操の敗戦を覆い隠すかのように「不利」などと書かれています。しかし、実際に歴史書『三国志』本文と裴松之の注釈を見ていると、曹操が赤壁で大敗したとは思えないような記録もあるのです。実は、曹操は208年12月に赤壁で敗れ、209年3月にに帰還したが、なんと209年7月には再び合肥に出陣しているのです。石井仁先生によると、この出陣は淮南の人心を安定させ、孫権との持久戦の体制を構築するための出陣だと見られる(石井仁〔著〕『曹操—魏の武帝』(新人物往来社 2000年)193頁参照)のですが、もし赤壁で大敗していたのであれば、たとえ出陣した軍の実態がどうであれ、虚勢だろうがなんだろうが驚異的な動きです。
また、曹操は「赤壁の戦いでは疫病が流行したため船を焼いて撤退したら、周瑜に虚名を得させてしまった」と述べています(『呉志』周瑜伝裴松之注所引『江表伝』)。この『江表伝』という史書の信頼性には疑問が残りますが、以上のような記録からすると、「本当に曹操軍は疫病で撤退しただけではないか」という考え方も出てくるのです。この判断は、現状ではなかなか難しいものがあります。
また、『呉志』のような、呉の武将たちの大活躍の記事にも少々注意が必要です。なんといっても、『呉志』の主な典拠(タネ本)は、呉国が編纂させ「呉がいかに正統な王朝であるか」を示す役割を担った韋昭『呉書』なのです。その記述をそのまま引き継いだため、『呉志』には韋昭『呉書』の特徴が現れていると考えられます。
『呉志』や裴松之の注に引用された韋昭『呉書』などの内容を見ると、吉川英治『三国志』などの小説と比べて極端に違うという印象を持つことは少ないでしょう。韋昭『呉書』にとってこの戦いは、戦果を強調してもしきれないものであったと考えられます。赤壁の戦いを「後漢の朝廷にのさばる曹操を撤退に追い込んだ戦い」と位置づければ、孫堅(孫権の父)以来「漢王室を正し、支えること」を初期の建前としていた孫氏の勢力の正統性を強調できるのです。呉の人々にとって、これほど素晴らしいことはありません(どうやら呉国の人々は自分たちの正統性に若干自信がなかったようです)。したがって、当然この戦いの『呉書』での主役はあくまでも呉の周瑜などの武将であり、さらに言えば彼らを使いこなした孫権なのです。そのような『呉書』の内容を受け継いだ『呉志』の記述をそのまま信用することは難しいことが理解できるでしょう。
『蜀志』は『魏志』と『呉志』の中間にあたる内容を有していますが、どうやら劉備を曹操のライバルと位置づけて構成されています。これは『魏志』も同様です。どうも陳寿が『魏志』の典拠となった王沈『魏書』などの性格を引き継ぎながら、蜀漢の正統性を『三国志』に忍び込ませようとしたためだと考えられます。呉を中心に描こうとしているように見える『呉志』呉主伝でも「劉備と孫権が協力して曹操を破った」とあり、「孫権が(中心となって)曹操を破った」などとは書かれていないことからすると、陳寿『三国志』の中ではそれなりに整合性が保たれているようです。
このように見ると、「赤壁の戦いについて、確実にわかっていることは何ですか?」と問われた際に、「208年12月に、孫権軍とにらみ合っていた曹操軍が撤退したこと」としか答えようがないのです。
また、曹操は「赤壁の戦いでは疫病が流行したため船を焼いて撤退したら、周瑜に虚名を得させてしまった」と述べています(『呉志』周瑜伝裴松之注所引『江表伝』)。この『江表伝』という史書の信頼性には疑問が残りますが、以上のような記録からすると、「本当に曹操軍は疫病で撤退しただけではないか」という考え方も出てくるのです。この判断は、現状ではなかなか難しいものがあります。
また、『呉志』のような、呉の武将たちの大活躍の記事にも少々注意が必要です。なんといっても、『呉志』の主な典拠(タネ本)は、呉国が編纂させ「呉がいかに正統な王朝であるか」を示す役割を担った韋昭『呉書』なのです。その記述をそのまま引き継いだため、『呉志』には韋昭『呉書』の特徴が現れていると考えられます。
『呉志』や裴松之の注に引用された韋昭『呉書』などの内容を見ると、吉川英治『三国志』などの小説と比べて極端に違うという印象を持つことは少ないでしょう。韋昭『呉書』にとってこの戦いは、戦果を強調してもしきれないものであったと考えられます。赤壁の戦いを「後漢の朝廷にのさばる曹操を撤退に追い込んだ戦い」と位置づければ、孫堅(孫権の父)以来「漢王室を正し、支えること」を初期の建前としていた孫氏の勢力の正統性を強調できるのです。呉の人々にとって、これほど素晴らしいことはありません(どうやら呉国の人々は自分たちの正統性に若干自信がなかったようです)。したがって、当然この戦いの『呉書』での主役はあくまでも呉の周瑜などの武将であり、さらに言えば彼らを使いこなした孫権なのです。そのような『呉書』の内容を受け継いだ『呉志』の記述をそのまま信用することは難しいことが理解できるでしょう。
『蜀志』は『魏志』と『呉志』の中間にあたる内容を有していますが、どうやら劉備を曹操のライバルと位置づけて構成されています。これは『魏志』も同様です。どうも陳寿が『魏志』の典拠となった王沈『魏書』などの性格を引き継ぎながら、蜀漢の正統性を『三国志』に忍び込ませようとしたためだと考えられます。呉を中心に描こうとしているように見える『呉志』呉主伝でも「劉備と孫権が協力して曹操を破った」とあり、「孫権が(中心となって)曹操を破った」などとは書かれていないことからすると、陳寿『三国志』の中ではそれなりに整合性が保たれているようです。
このように見ると、「赤壁の戦いについて、確実にわかっていることは何ですか?」と問われた際に、「208年12月に、孫権軍とにらみ合っていた曹操軍が撤退したこと」としか答えようがないのです。
【トラックバック(0)】
このブログ記事を参照しているブログ一覧: 赤壁の戦いについて(その4終)
このブログ記事に対するトラックバックURL: https://www.fujibi.or.jp/assets/files/exhi/3594blog/admin/mt-tb.cgi/27
【コメント(1)】
【コメントする】
※入力されたメールアドレスは記事に反映されず、ブログの管理者のみが参照できます。
※URLの入力は必須ではありません。
※なお、送られたコメントはブログの管理者が確認するまで公開されません。

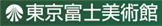

こんにちは。
三国志について、正史と演義両方からのアプローチ、非常に興味深く、面白く拝読致しました。
日本では、三国志を知っていると言う人でも、ほとんどが演義を知ってれば上等、普通は吉川三国志か、横山光輝のコミック三国志しか知らない。
というより、演義と正史の区別さえ付かないという人がほとんどですから、そうしたことは、話題にさえなりません。
私は史書を読んだことはありませんが、以前から、正史と演義のことは知っていました。
そして、演義の中の創作部分と史実との違いについて、非常に興味を持っていました。
今回、その辺りを書いてくださり、大変うれしく思っています。
演義と史実の違いがどれくらいあるか知ってみたい。
出来れば、正史も読んでみたい。
という思いで、こちらのブログを読んでいます。
今後とも、そうしたアプローチを楽しみにしています。