カテゴリー
赤壁の戦いについて(その3)
『蜀志』先主伝を見ますと、戦いの流れ自体は『呉志』と似ていますが、微妙に異なります。例えば、孫権軍と協力して曹操を打ち破ったことは共通していますが、その際に曹操軍の船を燃やしたとされるのです。また、赤壁の戦いの後、劉備・孫権連合軍は荊州の南郡に進出しますが、曹操軍で流行病が発生し撤退したとされるのはこの時とされています。
さらに関羽伝には、「孫権が劉備を救援し曹操を防いだので、曹操は軍を引いて撤退した」とあります。この記録から、特徴を二点指摘しておきたいと思います。
まず一点目は、関羽伝では「孫権は劉備を救援した」とされていることです。その点については、『魏志』武帝紀と似ています。ということは、この部分についての典拠(タネ本)が『魏志』と同じであった可能性があるということです。実は、陳寿が『三国志』を執筆していた当時、蜀漢に関する歴史書がなかったと考えられています。また、劉備・諸葛亮らはもともと蜀の人物ではないため、劉備の蜀征服以前についての史料が蜀漢には少なかったと思われます。『蜀志』の典拠が『魏志』と「カブった」としても、不思議ではありません。
二点目に、「劉備と孫権が曹操を防いだので、曹操は撤退した」と書かれていることです。この点については、『呉志』呉主伝に似ており、典拠(タネ本)が『呉志』と同じである可能性もあります。このように見ると、『蜀志』の記録上の立場は『魏志』と『呉志』の中間に位置することがわかります。
次回は、ここまで述べたことを踏まえた上で、どうしてこのような書かれ方になったのか、考えてみたいと思います。
さらに関羽伝には、「孫権が劉備を救援し曹操を防いだので、曹操は軍を引いて撤退した」とあります。この記録から、特徴を二点指摘しておきたいと思います。
まず一点目は、関羽伝では「孫権は劉備を救援した」とされていることです。その点については、『魏志』武帝紀と似ています。ということは、この部分についての典拠(タネ本)が『魏志』と同じであった可能性があるということです。実は、陳寿が『三国志』を執筆していた当時、蜀漢に関する歴史書がなかったと考えられています。また、劉備・諸葛亮らはもともと蜀の人物ではないため、劉備の蜀征服以前についての史料が蜀漢には少なかったと思われます。『蜀志』の典拠が『魏志』と「カブった」としても、不思議ではありません。
二点目に、「劉備と孫権が曹操を防いだので、曹操は撤退した」と書かれていることです。この点については、『呉志』呉主伝に似ており、典拠(タネ本)が『呉志』と同じである可能性もあります。このように見ると、『蜀志』の記録上の立場は『魏志』と『呉志』の中間に位置することがわかります。
次回は、ここまで述べたことを踏まえた上で、どうしてこのような書かれ方になったのか、考えてみたいと思います。
【トラックバック(0)】
このブログ記事を参照しているブログ一覧: 赤壁の戦いについて(その3)
このブログ記事に対するトラックバックURL: https://www.fujibi.or.jp/assets/files/exhi/3594blog/admin/mt-tb.cgi/24

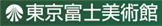

【コメントする】
※入力されたメールアドレスは記事に反映されず、ブログの管理者のみが参照できます。
※URLの入力は必須ではありません。
※なお、送られたコメントはブログの管理者が確認するまで公開されません。