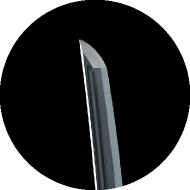北斎、広重、若沖、応挙 大集合 !
風神雷神から日本刀まで
本展は、本年9月1日から7日に開催されるICOM(国際博物館会議)京都大会を記念して、東京富士美術館が所蔵する3万点のコレクションの中から、日本美術の名品を展観するものです。東京富士美術館が所蔵する日本美術作品は、平安時代から近現代に至る多様な分野にわたっています。本展では千年の歴史の中で育まれてきた日本文化の豊穣な芸術世界のエッセンスをコンパクトにわかりやすく楽しむことができるように「カワイイ」「サムライ」「デザイン」「黄金」「四季」「富士山」など日本美術を特色づけるキーワードを通し、ニッポンのビジュツを俯瞰的に横断します。さらに刀剣をあたかも実際に手に持つようなスタイルで鑑賞できる刃文鑑賞特設ケースや、江戸時代に室内で灯明をあてて金屏風を鑑賞した様子を、VR技術を元にシミュレーション体験できる展示など、これまでの美術館の展示にはない、日本美術本来の鑑賞方法を新提案します。 絵画、浮世絵版画、漆工、刀剣、武具甲冑などの多彩な分野に及ぶ40点の名品を通して、日本の歴史と文化の多元性について理解していただけるとともに、日本美術の豊かさに触れる絶好の機会となるでしょう。
キモカワ "Kawaii" 日本美術 Japan
日本美術に登場するモチーフは、現代の私たちから見ると、ときに大変かわいく思われます。たとえば、円山応挙の描く犬や、長澤蘆雪の描くウサギは愛おしさを感じさせるカワイイ魅力を放っています。一方、曾我蕭白の描く仙人、東洲斎写楽の描く人物などは、デフォルメが強く、気持ち悪さや不気味さを持ちながらも、それゆえに可愛らしく感じられる、今でいう「キモカワ」的な印象を受けるかもしれません。「カワイイ」「キモカワ」の持つ多義的な魅力は、日本美術の特徴の一つともいえるかもしれません。
サムライ Samurai 日本美術 Japan
絵巻や屏風などの合戦絵に描かれた武士は、武具甲冑を身に帯び、日本独自の戦闘図の主人公として存在感を示しています。そしてもともと武士の身の回りの実用品でありながら、現在は「美術品」として鑑賞される武器や武具の数々。現在見ることができる武士の遺品は、消費され失われた多くの実用品とは一線を画し、いずれも当時の武士のこだわりや美意識を反映し、贅を尽くした逸品です。刀剣はぜひ武士が手に取って鑑賞したスタイルで名刀の美をあますところなくお楽しみください。
デザイン "Rinpa" Design 日本美術 Japan
俵屋宗達に始まり、尾形光琳が発展させ、酒井抱一や鈴木其一に代表される「琳派」の絵師。彼らの活動は、直接の師弟関係によらず江戸時代を横断し、京都から江戸へ広がり、絵画や工芸をまたぐという既成の流派の概念に収まらないものでした。宗達、光琳、抱一、其一と描き継がれた風神雷神図、其一は抱一までの二曲一双で並び立つ二神を、大胆に襖四面の広大な空間の表裏に描き分けます。斬新な発想力に由来する独自の造形=デザインに彼らの真骨頂があります。
黄金の国 Gold 日本美術 Japan
日本美術といえば、「金」というイメージがありませんか。絵画では金箔や金泥を用いた金屏風、工芸では金を贅沢に使った蒔絵装飾が有名です。古来から金の魅力は日本人の心をとらえ、とりわけ鎌倉時代以降、貴族や武士の生活を飾る美術工芸品に金が多用されました。絵画の装飾や、物語図の場面を仕切る金雲などにも金は多用されました。ここではこれらの屏風が制作された当時、室内の灯明の光で鑑賞した際に、光を反射する金の輝きが絵画の鑑賞に与えた効果を感じてください。
四季 Four Seasons 日本美術 Japan
季節の表現は、日本美術の歴史と広がりにおいて大きなウェイトを占めています。古くは平安時代から、自然描写と相まって季節を描くことは広く行われ、とりわけ大画面の屏風では、六曲一双の向かって右側に「春→夏」を、左側に「秋→冬」を描くことが通例となりました。絵画・工芸など幅広いジャンルで、貴族や武士、そして庶民に至るまで人気の画題でした。四季の表現には、季節を表す動植物や情景などが用いられますが、その描写の発展には中国絵画の影響も見られます。
富士山 Mt. Fuji 日本美術 Japan
富士山はその圧倒的な存在感で、古くから人々を惹きつけてきました。名所絵として、あるいは富士信仰の対象として、日本美術のなかでもしばしば描かれています。江戸後期に、大胆な構図や遠近法を用いた葛飾北斎の「冨嶽三十六景」、諸国を旅して実地のスケッチを重ねた歌川広重の「東海道五十三次」などが出版され、大変な人気を博します。特に、北斎が夏の赤富士を描いた「凱風快晴」や「山下白雨」、荒れ狂う大波と富士を描いた「神奈川沖浪裏」は、日本を代表する美術作品といえるでしょう。
開催概要 ABOUT
ICOM京都大会開催記念 京都新聞創刊140年記念 東京富士美術館所蔵
百花繚乱 ニッポン×ビジュツ展
北斎、広重、若冲、応挙 大集合!風神雷神から日本刀まで
This Is Japan In Kyoto From The Tokyo Fuji Art Museum Collection
会期
2019年8月25日(日)〜9月29日(日)
開室時間
午前10時 ~ 午後6時
※金曜日は午後7時30分まで(入場はそれぞれ30分前まで)
休館日
月曜日、祝日の場合は翌日(ただし、9月2日は臨時開館)
主催
京都府、京都文化博物館、京都新聞、テレビ大阪
共催
京都市
後援
(公社)京都府観光連盟、(公社)京都市観光協会、KBS京都、エフエム京都
協賛
株式会社ローソンエンタテインメント
企画協力
東京富士美術館
入場料
一般 1,200円 (1,000円) 大高生800円(600円) 中小生400円(300円)
※()は前売券及び20名以上の団体料金
※ 未就学児は無料。(要保護者同伴)
※前売券は2019年6月24日(月)から8月24日(土)まで販売。(会期中は当日券のみ)
※障害者手帳等をご提示の方と付き添い1人までは無料
※学生料金で入場の際には学生証をご提示ください
※上記料金で、2階総合展示と3階フィルムシアターもご覧いただけます。(催事により有料の場合があります)
主な入場券販売所
京都文化博物館、ローソンチケット(Lコード:52245)、主要プレイガイド
ACCESS MAP
東京富士美術館について Tokyo Fuji Art Museum
東京富士美術館は、1983年に開館した東京都八王子市にある総合的な美術館です。日本・東洋・西洋の各国、各時代の絵画・版画・写真・彫刻・陶磁・漆工・武具・刀 剣・メダルなど様々なジャンルの作品約30000点を収蔵しています。ルネサンス時代からバロック・ロココ・新古典主義・ロマン主義を経て、印象派・現代に至る西洋絵画500年の流れを一望できる油彩画コレクションと、写真の誕生から現代までの写真史を概観できる写真コレクションは当館最大の特徴となっています。 展覧会活動としては、「世界を語る美術館」をモットーに世界各国の優れた文化を新しい視点から紹介する海外文化交流特別展を国内外で活発に開催しています。