今からおよそ1800年前、広大な中国大陸を三分して魏(ぎ)・呉(ご)・蜀(しょく)の三国が覇権を争いました。劉備(りゅうび)・関羽(かんう)・張飛(ちょうひ)の三兄弟や名軍師・諸葛亮(しょかつりょう)(孔明(こうめい))、乱世の梟雄(きょうゆう)・曹操(そうそう)、南海の龍・孫権(そんけん)ら英雄・名将・知将が活躍した「三国志」の世界は、私たち日本人に身近なものです。
本展では、「三顧(さんこ)の礼」「赤壁(せきへき)の戦い」といった有名な場面を描いた文学や絵画の世界を紹介するコーナーと、当時の武器や生活などを伝える貴重な考古出土品を展示するコーナーの2部構成で、「三国志」世界の全貌にせまります。
「物語でたどる三国志」では、小説『三国志』の名場面をたどります。中国の明・清時代の美術工芸品や日本美術の名作をはじめ、三国志ゆかりの地の風景映像なども活用し、魅力ある英傑たちの人間像とストーリーを紹介します。
「出土品でたどる三国志」では、古戦場や史跡からの出土品によって実際の歴史上の魏・呉・蜀による三国鼎立(ていりつ)の時代にせまります。現代に残る遺跡や墓から出土した刀剣や鏃(やじり)などの武器、金印や装身具、副葬品などの貴重な品々は、私たちに三国時代に生きた英傑たちの息づかいを感じさせてくれることでしょう。
中国全土の2市9省34カ所に及ぶ博物館・機関から出品される約150点のうち、約3分の1にあたる53点が国家一級文物と呼ばれる日本の国宝に相当する大変貴重な作品です。さらに日本国内の博物館が所蔵する三国志関連作品約60点ほかを加えた総点数220点の作品で、歴史と文学の両面から「三国志」の世界を総合的に紹介する“世界初”の試みとなる本展にご期待下さい。
【展覧会構成】
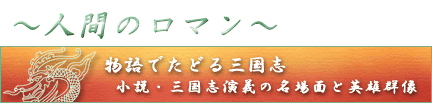

河北省涿県。劉備の生まれ故郷とされる村に建つ三義廟。近郊には有名な三国志演義の名場面・桃園の誓いの舞台となった張飛廟もある。

黄巾(こうきん)の乱(らん)が激しさを増していた頃、漢王室の末裔である劉備(りゅうび)は、涿県(たくけん)の街で出会った関羽(かんう)・張飛(ちょうひ)と桃園で義兄弟の契りを交わし、「国のため、民のために戦い、願わくは同年同月同日に死なん」と誓いました。このことを「桃園の誓い」と呼びます。劉備らは義勇兵を率いて黄巾の乱鎮圧に活躍しました。その後、董卓(とうたく)が登場し暴政をしいたため、袁紹(えんしょう)・曹操(そうそう)・孫堅(そんけん)(孫権(そんけん)の父)・劉備らによって反董卓軍が結成され、虎牢関(ころうかん)で呂布(りょふ)らと激闘を繰り広げましたが、董卓は貂蝉(ちょうせん)の「連環(れんかん)の計(けい)」によって仲違いした呂布に殺されました。董卓の登場以降、後漢は群雄割拠の時代を迎えましたが、その中から皇帝を擁立した曹操が抜け出し、袁紹を官渡(かんと)の戦いで破ります。この時、曹操に降伏していた関羽が活躍して恩を返し、曹操配下の妨害を超人的な武力で乗り越えて、劉備のもとへ戻っていったのです。
 |
呉暁峰
«関公読春秋坐像»
安徽省博物館 |
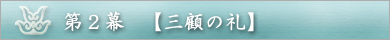
袁紹(えんしょう)のところから離れた劉備(りゅうび)は荊州(けいしゅう)の劉表(りゅうひょう)を頼りました。劉表は歓迎してくれましたが、劉備は平和な暮らしの中で腿に肉がついてしまったことを歎きました(「髀肉(ひにく)の嘆(たん)」)。劉表の重臣たちから警戒された劉備は宴席で暗殺されそうになり、「不幸を呼ぶ馬」とされた的廬(てきろ)に乗って檀渓(だんけい)という川を飛び越えて難を逃れました。その後、司馬徽(しばき)・徐庶(じょしょ)の推薦を受けて、劉備は諸葛亮(しょかつりょう)(孔明(こうめい))の廬(いおり)を三たび訪れ、ようやく会うことができました。これを「三顧の礼」と言います。劉備の「民を救いたい」との思いにうたれた孔明は「天下三分(てんかさんぶん)の計(けい)」を説いて劉備に仕えました。その頃、曹操(そうそう)は北方を平定し、荊州に迫っていました。劉表が亡くなり、後を継いだ子の劉琮(りゅうそう)はすぐに曹操に降伏します。劉備は孔明の策を用いて博望坡(はくぼうは)で曹操軍を破りましたが、結局は民を引き連れて敗走。趙雲(ちょううん)は曹操軍に囲まれながら劉備の子・劉禅(りゅうぜん)を救い、長阪橋(ちょうはんきょう)では張飛(ちょうひ)が曹操軍を怒鳴りつけただけで撤退させました。そして、孔明が孫権(そんけん)のもとへ派遣され、赤壁(せきへき)の戦いへとむかっていくことになるのです。

戴進«三顧茅廬図(三顧の礼)»北京・故宮博物院

孫権(そんけん)のもとに赴いた諸葛亮(しょかつりょう)(孔明(こうめい))は、孫権の家臣たちと舌戦を繰り広げながら、孫権を説得し曹操(そうそう)との戦いを決意させようとします。孫権は軍の責任者・周瑜(しゅうゆ)を呼び寄せて意見を聞き、開戦を決断し、軍を赤壁に出陣させました。孔明の才能を警戒する周瑜は、「十万本の矢を調達する」という難題を孔明にふっかけ、孔明は「三日以内に」と約束します。そして三日目、孔明は魯粛(ろしゅく)とともに曹操軍に向けて船を出し、そこで浴びた矢を集めて十万本の矢を調達しました。周瑜・孔明ともに、曹操に勝つためには火計しかないと考えますが、そのために周瑜は曹操を油断させようとして「苦肉(くにく)の計(けい)」をしかけ、黄蓋(こうがい)にウソの降伏の手紙を曹操に送らせました。その頃、曹操は船上で宴会を開き、「短歌行(たんかこう)」と呼ばれる詩を作って歌っています。火計の準備をした周瑜は東南からの風が吹かないため困っていましたが、孔明は七星壇(しちせいだん)を築かせてその上で祈り、風を吹かせることに成功します。それを期に、周瑜の率いる軍が鎖でつながれた曹操軍の船団を攻撃し、勝利を収めました。これが「赤壁の戦い」です。

仇英«赤壁図»遼寧省博物館
曹操(そうそう)は敗走しましたが、その行く先々で諸葛亮(しょかつりょう)(孔明(こうめい))が配置した趙雲(ちょううん)・張飛(ちょうひ)に襲われ、華容道(かようどう)では関羽(かんう)に道を阻まれます。曹操は、一旦は観念しましたが、関羽が信義を重んずることにつけいり、以前関羽にかけた恩義を訴えたため、関羽は曹操を見逃しました。その後、劉備(りゅうび)は荊州(けいしゅう)南部を制圧し、孫権(そんけん)の妹と結婚して孫権との関係を深めます。赤壁で敗れた曹操は、それでもまだ劉備・孫権に比べて優越している力を見せ付けるように銅雀台(どうじゃくだい)を完成させました。劉備は「天下三分(てんかさんぶん)の計(けい)」の実現に向けて益州(えきしゅう)へと進撃しますが、孫権はこの隙に荊州を奪おうと考え、妹の孫夫人を騙して呼び戻しました。孫夫人は劉禅(りゅうぜん)を連れて行こうとしますが、趙雲が奪い返しました。劉備は軍師の 統(ほうとう)を落鳳坡(らくほうは)で失うなどの犠牲を払いながらも益州を征服し、曹操からは漢中(かんちゅう)も奪い取りました。そして、劉備の先祖で前漢(ぜんかん)を創始した劉邦(りゅうほう)も就いていた漢中王に即位し、「天下三分」の足場を築いたのです。 統(ほうとう)を落鳳坡(らくほうは)で失うなどの犠牲を払いながらも益州を征服し、曹操からは漢中(かんちゅう)も奪い取りました。そして、劉備の先祖で前漢(ぜんかん)を創始した劉邦(りゅうほう)も就いていた漢中王に即位し、「天下三分」の足場を築いたのです。

荊州(けいしゅう)を任されていた関羽(かんう)が曹操(そうそう)を攻撃すると、関羽を恐れた曹操と孫権(そんけん)は手を結び、挟み撃ちにして孫権軍が関羽を捕らえて処刑しました。その直後に曹操も関羽の亡霊などに怯えながら亡くなります。後を継いだ曹丕(そうひ)は後漢(ごかん)の皇帝に位を譲らせて皇帝となり、魏(ぎ)を建てました。その際、後漢の皇帝が殺されたと聞いた劉備(りゅうび)も皇帝となりましたが、周囲の反対を押し切って関羽の仇討(あだう)ちのために呉を攻撃しようとします。しかし、張飛(ちょうひ)が部下によって殺された上に、夷陵(いりょう)の戦いで大敗。病に倒れた劉備は諸葛亮(しょかつりょう)(孔明(こうめい))に「息子に才能がないなら、君が皇帝になれ」という遺言を残して亡くなり、孔明はその信頼に応えて劉禅(りゅうぜん)に忠節を尽くし、漢王朝復興のために戦うことになります。孔明は蜀(しょく)に従わない南蛮(なんばん)へ軍を進め、王の孟獲(もうかく)を七回捕らえて七回解き放ち、「心を攻める」戦略をとって服従させたのです

234年8月、諸葛亮(孔明)が没した陝西省、五丈原

234年8月、諸葛亮(孔明)が陣没した陝西省、五丈原の丘から望む

五丈原、諸葛亮(孔明)の本陣の跡地
南蛮(なんばん)平定後、諸葛亮(しょかつりょう)(孔明(こうめい))は劉禅(りゅうぜん)に「出師(すいし)の表(ひょう)」を奉って魏(ぎ)を倒すための北伐に向かい、蜀(しょく)軍は順調に魏の領土を征服していきました。魏の援軍を街亭(がいてい)で防ぐ時、孔明は馬謖(ばしょく)を責任者にしますが、馬謖は孔明の指示を無視して山上に陣取ったため司馬懿(しばい)に給水路を断たれて大敗し、孔明自身も「空城(くうじょう)の計(けい)」で何とか難を逃れるような状態で、一回目の北伐は失敗に終わりました。馬謖は孔明が期待する人材でしたが、孔明は軍法違反で処刑しました(「泣いて馬謖を斬(き)る」)。その後も孔明はたびたび出撃し素晴らしい策略の冴えを見せますが、味方に足を引っ張られたりしたため、うまくいきませんでした。234年、孔明は呉との共同作戦の約束を取り付けて五丈原に出撃し、魏の司馬懿とにらみ合いを続けます。しかし、せっかく出撃した呉は情勢不利と見るやあっさりと撤退。その知らせを聞いた孔明は病に倒れました。姜維(きょうい)に勧められ、火を灯して北斗七星に延命を祈りましたが、魏延(ぎえん)が乱入してきたために火が消えて失敗。結局、孔明は五丈原で亡くなり、撤退の際に襲いかかる魏軍を孔明の木像で驚かせて逃走させたのです(「死せる孔明、生ける仲達(ちゅうたつ)を走らす」)。
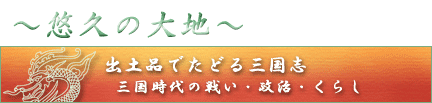

223年、諸葛亮(孔明)に劉禅を託した後、劉備が亡くなった長江流域の白帝城の現在の姿。劉備ひきいる蜀漢は、漢王朝の正統な後継を自認して、強大なライバル、魏に戦いを挑み続けた。
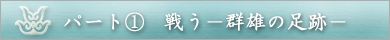
- [1. 剣(つるぎ)-武器]
- [2. 軍備-騎馬・兵士・城塞]
西暦184年、宗教結社の太平道(たいへいどう)を中心とする黄巾(こうきん)の乱(らん)が起きました。乱自体は一年ほどで鎮圧されますが、後漢(ごかん)ではこの後も反乱が続発したため、それまで政治・経済・文化の中心であった黄河(こうが)中・下流域(中原(ちゅうげん))は疲弊しました。董卓(とうたく)登場以降の混乱の中で豪族たちの群雄割拠がはじまると共に、城塞を築いて自衛する荘園(しょうえん)を基盤に自給自足する貴族たちも現れ始めます。また、戦乱とともに漢民族と北・西方、また南方の民族が入り交じり、後の五(ご)胡(こ)十(じゅう)六(ろく)国(こく)時代の争乱の源流となりました。当時の重要な戦いとしては、曹操(そうそう)の覇権の足場を築いた200年の官(かん)渡(と)の戦い、曹操と孫権(そんけん)・劉備(りゅうび)連合軍が決戦を行った208年の赤壁(せきへき)の戦い、諸(しょ)葛(かつ)亮(りょう)(孔(こう)明(めい))が亡くなることになる234年の五丈原(ごじょうげん)の戦いなどがあります。特に赤壁の戦いは、天下統一目前だった曹操が孫権・劉備連合軍に敗れたことにより、天下三分の形勢が確立し三国時代の幕開けとなった戦いです。このパートでは、赤壁の古戦場から出土した鏃(やじり)などの当時の武器・武具、また後漢から西(せい)晋(しん)時代の墳墓に副葬された騎馬や兵士俑、楼閣(ろうかく)などによって、激動の戦乱の痕跡をたどります。

«車馬儀仗隊の主騎»甘粛省博物館

«四  形箭鏃»(赤壁古戦場より出土した矢じり)赤壁市博物館

呉の孫権が築いた石頭城。呉の首都・建業(現在の南京)を防衛する拠点であった。この時代、長江流域は呉の孫権が推進した開発により農業・商業が発展をはじめており、周辺の遺跡・墳墓からはこの地域特有の多様で豊富な出土品が発掘されている。
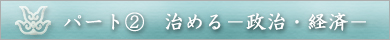
- [1. 為政者-曹家ゆかりの品]
- [2. 荘園-貴族の生活]
- [3. 政(まつりごと)-文字・印章]
- [4. 商う-通貨・交易]
- [5. 生産-農耕・牧畜]
『三国志』の時代は「華麗なる暗黒時代」でした。寒冷化する気候、絶え間ない戦乱とそれらによる生産力の低下、董卓(とうたく)の暴政による貨幣経済の崩壊、戦争優先の国家体制などが人々の生活を直撃したのです。そのような危機の中で新たな制度が形作られ、三国の各国では貨幣作りも試みられて経済活動が徐々に発展し、諸外国との往来も行われました。また、長江流域では呉(ご)の孫権(そんけん)による開発が進んで農業や商業が発展しはじめています。このパートでは三国時代の為政者である貴族の生活用品、また政治・経済の活動を示す木簡(もっかん)や印章、貨幣などの出土品、そして社会を根本から支える農業生産活動を今に伝える副葬品などを展示します。

«銀縷玉衣»亳州市文物管理所
 |
«「魏帰義 侯」金印» 侯」金印»
甘粛省博物館 |
 |
«玉杯»
洛陽博物館 |

魏の都、鄴城。204年曹操はこの地を都と定め、銅雀台を築いた。210年以降、文学活動の拠点となり、建安文学と呼ばれる文学が盛んになった。

- [1. 食べる-三国の食文化]
- [2. 装う-ファッション]
- [3. 楽しむ-音楽・芸能]
- [4. 祈る-祭祀・道教・仏教]
三国時代は文化面においても一大変革期でした。曹操(そうそう)の宮廷で盛んになった建安文学(けんあんぶんがく)は後の時代にも多大なる影響を与え、特に曹(そう)植(ち)は「杜甫(とほ)以前の最高の詩人」とされます。また、庶民にとって悲惨な戦乱の時代の中で、儒教にも変革の波が襲い、宗教に救いを求めた人々の間に道教・仏教も広まりはじめています。また、いつの時代にあっても変わらぬ民衆の暮らしも存在していました。このパートでは、三国時代の生活・文化のさまざまな側面を出土品によってたどることにします。

«黄金製装身具(珠)»湖南省博物館
 |
«説唱俑»
成都市新都区
文物管理所 |
【出品点数】 約220点(関連資料等含む)
※展示構成・出品内容等は予定のため、都合により変更する場合があります。
|