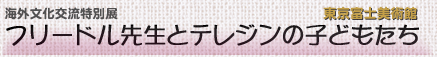
テレジンの収容所 テレジン強制収容所は1941年から1945年にかけて、西ヨーロッパのユダヤ人たちをアウシュヴィッツに移送する中継地となっていました。14万4000人のユダヤ人がテレジンに送られ、四分の一近い3万3000人がこの町で死亡し、8万8000人がアウシュヴィッツをはじめとする絶滅収容所に送られていきました。
まさに「地獄の控え室」と称されたテレジンで、1万5000人もの子供たちが恐怖の生活を経験し、生きながらえたのは、ほんの一握りの子供たちでした。 両親がアウシュヴィッツへ送られて悲しみと不安に喘ぐ子供や、食料も乏しく日に日に痩せ衰えて飢餓に瀕する子供たち。
さらに焼却炉では焼き尽くせないほどの遺体が散在する光景は、まさに地獄絵図そのものだったに違いないでしょう。 しかし、フリードルはその「死」の極限状態にありながらも、厳しい監視の目を逃れて、数百人の子供たちに絵を教え、自らも創作活動を行ったのです。
「目を閉じて、楽しかったことを思い出すのよ!」「今は辛いでしょう。でも、明日になれば、きっと、良い日になるわ。希望をもって生きましょう!」 絵の具が無ければ糸くずで描き、紙が無ければゴミくずを拾って描きました。 “描くことが生きることの証”------ フリードルは絵を描くことを通して子供たちに『希望の灯火』を与えていったのです。 そして、子供たちの残したそれらの作品は、その短い人生の記念碑となりました。
1944年10月6日、移送番号167を付けられたフリードルはアウシュヴィッツへ強制移送され、同年10月9日、ビルケナウ(アウシュヴィッツ第二収容所)のガス室でその尊き生涯を閉じました。
Copyright (c) Tokyo Fuji Art Museum 2002. All rights reserved. |






